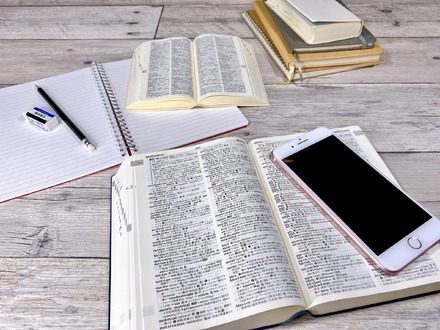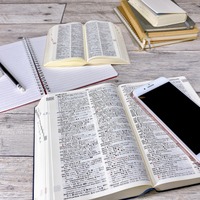この「東大生が答えるお悩み相談室」シリーズは、読者から寄せられた質問やお悩みについて、東京大学に在学する現役東大生たちが答える動画企画だ。インタビュー形式で、読者・視聴者から届いた勉強や受験、大学生活などに関するさまざまな質問に答えていく。
今回は、偏差値35から2浪して東京大学に合格し、現在はカルペ・ディエムの代表取締役社長を務める東京大学経済学部4年生の西岡壱誠氏と、東京大学教育学部3年生の新藤篤隼斗氏の対談だ。東京大学進学に関心のある中高生だけでなく、受験、勉強、大学生活などに漠然と不安を感じている人にも、ぜひご覧いただきたい。
「シケ対」って何?
--質問です。「受験勉強と東大の勉強 どちらが大変でしたか?どちらが楽しいですか?」。
西岡新藤:受験勉強のほうが大変だけど楽しい!
新藤:やっぱり受験勉強と比べちゃうと、どうしても大学の勉強はどうしても楽に感じちゃいますよね。
西岡:これは東大生が勉強をしていないというわけじゃなくて、「受験勉強が大変だ!」って話ですよ。二浪に何言わせてるんだよ!(笑)
新藤:実際、自分が受験生の時は一日に平均10時間くらいやっていましたね。
西岡:よく、何時間勉強したら東大合格できますかっていう質問あるんだけど、何時間勉強したら、ここまで勉強したら東大に絶対合格できるっていう世界じゃないから困るよね。
新藤:僕は勉強時間というよりは、勉強量を重視していました。今日はここまでやるぞっていうノルマを決めて集中してやっていましたね。
西岡:それでいうと大学の勉強って範囲が明確だよね。
新藤:そうですね。しかもその範囲が大学受験の勉強と比べたら多くないから、どっちが大変かとか、好きかと聞かれると、やっぱり受験勉強と言わざるを得ないという感じです。ただ医学部に行っている友達の話を聞いていると、テスト勉強がめちゃめちゃ大変で、遊んでいるときや飲み会をしているときでも勉強の話をしていましたね。
西岡:確かに理系のほうが厳しめだというのはあるだろうね。あと東大は試験の対策システムがしっかりしているよね。
新藤:そうですね。東大にはシケ対という制度があって、そのおかげで必死に勉強しなくても大学の授業についていけるようになっています。
西岡:特に法学部だとよりシステムがしっかりしていて、ひとりひとりにメールで「ここからここまでの範囲のプリント作成お願いします」って連絡が来て、それやらないとマジで怒られたり、シケ対の中で市民権がなくなってその制度に参加できなくなったりする。そうすると、ほかの授業のプリント等がもらえないからもっと大変になるんだよね。こんな感じでシステムがしっかりしているのは、さすが法学部だなと思いますね。
新藤:逆に教育学部だと試験がなくてほとんどがレポートか課題提出なので、あまりシケ対の制度はないですね。ただ自分は1、2年のころは理系だったので、シケ対の制度のおかげで、「みんなで協力しよう」という雰囲気ができていて、周りと高めあっていましたね。
西岡:それはすごいわかるわ。シケ対になるのは名門中高出身の人が多くて、そうすると同じ中高だった友達や先輩から過去問とかプリントをもらえるんだよね。そういうのがあってうまく機能しているよね。
新藤:逆に公立出身の僕は知り合いがまったくいないので、過去問やプリントを全然もらえなくて。僕は頼りにならなかったと思います(笑)。
西岡:あるよね。俺は逆に周りに知り合いがいないから、シケ対をやったおかげでほかの人と仲良くなりに行っていた。コミュニケーションをとれるから、それで交流の幅が広がったっていうことが結構あった。
新藤:なるほど自分もそれをやっていれば交流が広がったかもですね。
西岡:ただ難しいところもあって、大学の単位って相対評価だから、周りの人ができていると自分の成績も下がっちゃうんだよ。だから、ほかのクラスの人には過去問とかプリントを見せないようにしよう、みたいな風潮があることも。そこでコミュニケーションが大事になってきて、「○○の授業プリントありませんか? こっちは××の授業の過去問出します!」みたいな感じで交渉をしていましたね。
新藤:やっぱり勉強ができるかどうかだけじゃなくて、人付き合いの力も必要なんだなと思いますね。