名古屋芸術大学で、2025年9月から本格的に始動した「起業家育成」プログラム。なぜ、芸術を専門とする大学でビジネスを学ぶのか、意外に思われるかもしれない。ところが今、ビジネスの最前線では芸術を通じて培われる感性や美意識が求められており、芸術大学での「起業家育成」はまさに最先端の取組みだと言える。
名古屋芸術大学が目指す人材育成の全貌と、それが学生の未来にどうつながるのか、キャリアセンター長・中川直毅教授、プログラムの講師を務める起業家・藤本広敬氏(Mdesign holdings代表取締役)、卒業生の日本画家・磯部絢子氏に話を聞いた。
インタビュイー:
中川直毅 教授(教育学部/キャリアセンター長)
藤本広敬 氏(「起業家育成」プログラム講師/Mdesign holdings代表取締役)
磯部絢子 氏(美術学部日本画コース卒業後、大学院美術研究科美術専攻日本画制作研究領域/日本画家)
名古屋芸術大学が目指すのは「二刀流」
--芸術を専門とする大学で、なぜ「起業家育成」のプログラムを始めることになったのか。まずはその経緯からお聞かせいただけますか。

中川教授:名古屋芸術大学が「起業家育成」のプログラムを始めることになった背景には、大学として学生のキャリア支援を今以上に強化し、社会で活躍できる人材を育成したいという強い思いがあります。私は上場企業で人事や法務の経験を積んできましたが、芸術を専攻した人材が感性や美意識に優れている一方、ビジネスに関する知識が十分にないため、その才能を生かしきれていないと感じる場面が少なくありませんでした。その後、名古屋芸術大学のキャリアセンター長に着任してからは、卒業生から「もっと早く経営に必要な実務スキルを学んでおきたかった」といった声も数多く耳にしました。
そこで私は、名古屋芸術大学のキャリア支援において、芸術の専門分野を学ぶ「大きな刀」に加え、ビジネススキルを「小さな刀」として身に付ける「キャリア二刀流」というコンセプトを提唱することにしたのです。
--今回始動するプログラムは、なぜ「起業家育成」と名付けられているのですか。
中川教授:これまでアーティストといえば、一般的には個人でフリーランスのイメージが強かったかもしれませんが、今の学生たちの間では、アートを生かしてビジネスを立ち上げたいというニーズが高まってきているように感じます。
今日来てくださっている藤本さん、磯部さんのように第一線で活躍している方をロールモデルとして講演会を開くなど、これまでもそうした学生の夢を広げる取組みはしてきました。ですがこれからは、実務レベルでよりリアルに、起業に必要な基礎知識を学べる講義を充実させることで、起業へのハードルを下げていきたいと思ったのです。
もちろんこのプログラムで身に付ける知識は、起業のためだけではありません。企業に勤めることになったとしても、あるいは個人でアーティストとして生きていくうえでも間違いなく武器になる内容ばかりです。
ビジネスの最前線が重視するのは「感性」「直感」「美意識」
--親世代には、「芸術で食べていくのは難しい」という価値観が根強いと思います。ところが今は、AIが加速度的に進化し、論理力や情報処理力が人間を上回ろうとしており、これまで安泰だとされてきた仕事もAIに奪われるのではないかとの懸念が高まっています。経営者のお立場から、芸術大学出身者だからこそできる、AIに代替できない仕事とはどのようなものだとお考えですか。
藤本氏:今はグローバルエリートほど積極的にアートを学び、感性や直感、美意識を大切にしている時代です。私は中古車販売のビジネスで起業し、現在は飲食など多様な分野でビジネスを展開している経営者です。
その立場上、経営者同士で交流する機会が多いのですが、優れた経営者ほど、意識的にアートに触れる機会をもち、美意識や感性を大切にしていると感じます。日頃からアートを通じて感性を磨くことが、素晴らしいひらめきや発想、常識にとらわれない行動力を生み出し、ビジネスの成功に結びついていると思うのです。
ですから、私も含めて経営者仲間はよく、「もっと若い頃からアートに触れておけばよかった」と言っています。学生時代にアートを学び、それを早くから経営に生かせていたら、と。人間の感性の領域は、AIではカバーできません。これからの時代こそ、アートを専門とする教育の価値はますます貴重になり、あらゆる分野から必要とされてくるのではないでしょうか。

中川教授:『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』という大ベストセラーを書いた山口周氏はその著書の中で、「これまでのような『分析』『論理』『理性』に軸足を置いた経営、いわば『サイエンス重視の意思決定』では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはできない」と述べています。
そして、「『アートを担う人材』と『サイエンスを担う人材』が組み合わさることで、組織の経営品質が高まるのだ」と。さらに、「私たち日本人は類い稀な『美意識』を潜在的にもった民族で、その点については自信をもつべきだ」とも言っています。
この点で、日本の芸術大学には、まさにその両方の素養をハイブリッドにあわせもてるポテンシャルの高い人たちが集まっていると言えます。これは計り知れない強みです。このような人材が芸術大学から多く輩出されることは、日本という国にとっても、課題解決や新たな価値創造につながる大きな可能性を秘めていると思うのです。
実務家講師陣からビジネスの基礎を学ぶ
--ではここからは、「起業家育成」プログラムの概要について教えてください。
中川教授:複数の実務家を担当講師とする15回のリレー講義で、法律、金融、サステナビリティ、雇用、ビジネスプランの策定などについて学んでいきます。
第2回:日常生活と法学(1)「日常生活における法的リスク」
第3回:金融論(1)「金融の基礎」
第4回:金融論(2)「金融のしくみ」
第5回:金融論(3)「企業の資金調達」
第6回:金融論(4)「株式・債券・投資信託」
第7回:金融論(5)「経済成長期の金融システム」
第8回:金融論(6)「金融商品を用いた資産形成」
第9回:環境経済論(1)「企業における環境保全」
第10回:環境経済論(2)「サステナビリティビジネス」
第11回:産業社会学(1)「就業形態の多様化」
第12回:産業社会学(2)「新しい働き方と多様な環境での働き方」
第13回:産業社会学(3)「雇用政策」
第14回:起業(2)「ビジネスプラン」
第15回:日常生活と法学(2)「弁護士の役割と活用」
また、これらに加えて、ビジネス界で活躍する経営者などを招いた演習・講義を実施したり、企業訪問や交流パーティーなど企業との結びつきを広げ、深める機会を提供したり、起業を考える学生への相談窓口を設置したりするほか、少人数制のゼミ形式で公務員試験対策や就活スキルの向上といったサポートを行うなど、起業と就活両方に手厚い支援体制を整えています。
藤本氏:私は第1回と第14回の講義を担当します。学生が起業する際、「何を避け、何をすべきか」を具体的に指導していきます。他の講義で経済や法律といった起業に必要な実務的な専門知識を学べるので、私の授業では経営者としての失敗も含めた実体験を織り交ぜつつ、起業の醍醐味と厳しさの両面を伝えていけたらと思っています。中でも、商品やサービスの「コンテンツ」の価値だけで勝負するのではなく、なぜそのビジネスを始めたのかという「コンテクスト」(文脈)、つまり社会的意義をストーリーとして明確に伝えることの重要性を共有したいですね。
というのも、ビジネスを成長させていくには「三方よし」がカギになるからです。「三方よし」とは、江戸時代中期に滋賀県(近江国)の商人たちが全国に広げた商いの哲学で、売り手だけが得をするのではなく、買い手にも満足してもらえ、さらにはその商いを通じて社会にも貢献できる。これこそが持続可能なビジネスであり、良質な事業であるという教えです。学生たちには「三方よし」の視点をもち、お客様や社会全体から応援される起業家になってほしいです。
「アーティストとして生きていく」ための指南術でもある
--卒業生として、母校で「起業家育成」の講義が始まることについてどのように感じていらっしゃいますか。

磯部氏:私が大学を卒業する頃は「就職するとアーティストが減る」、つまり「就職=アーティストとして生きていくことを諦めなければいけない」と捉える風潮が学内にもありました。ですから、このようにアートとビジネスを両立できる環境が整ってきたことに、大きな期待を感じずにはいられません。
私もかつてはフリーランスとして個人で活動していましたが、アーティストという特殊な職業柄、インターネットで調べてもほしい情報が見つからず、作品が売れたときの領収書の書き方から確定申告、さまざまな書類作成など、誰に相談すれば良いかもわかりませんでした。こうした業務を自力で何とかしようと多くの時間を費やしてきただけに、学生時代からビジネス上の実務知識について学べることは、アーティストとしての選択肢を広げ、自立を支援するうえで非常に有益だと思います。
--今、磯部さんは東京の会社の社員としてリモート勤務などの協力を受け、その会社の仕事と両立しながら制作活動を続けていらっしゃるのですね。
磯部氏:はい、そのとおりです。先ほど藤本さんのお話にもあったように、日本の企業も経営者を中心に、作品を買ってくれたり、制作活動を支援してくれたりと、アートに対する理解が深まってきていることを実感しています。私もこうしてリモートワークで制作と両立ができているのは本当にありがたいです。
藤本氏:経営者の立場から言うと、アーティストとの関係は単なる支援ではなくパートナーとして、幅広いビジネスの視点から、より作品が認められやすい状況を戦略的に作り出す方法を編み出したい。そこから新たな価値を生んでいきたいんですよね。
これまでのアーティストというのは、自分の作品だけで孤高に勝負しようとする人が多かったと思います。けれど、アートとビジネス両方の視点から、どうやってその価値を高めていくかを考えることで、制作活動が持続可能になるだけでなく、活動の規模を広げる可能性も十分あると思うのです。
中川教授:藤本さんのようにビジネスの最前線を知っている実務家の講師陣から直接講義を受けることで、学生たちは多角的な視点を身に付け、新たな価値の生み出し方に気付くことができるわけですから、この講義は「アーティストとして生きていく」ための指南術とも言えるかもしれません。
「アート」と「起業家育成」の融合で育つ人材が新しい価値を創造する

--この「起業家育成」講義を通じて、学生たちにはどのような成長を期待しますか。
中川教授:実務的なスキルが身に付くことはもちろんですが、私のいちばんの願いは、「自分は社会で十分やっていける」という自信をもってもらうことです。それには「攻め」と「守り」両方の姿勢が必要です。自身の興味や問題意識に基づいた目標に向かって進んでいこうとする意志や行動力といった「攻め」、しかしその一方で社会のさまざまなリスクを回避するために必要な知識という「守り」。この両方を学ぶことで、自信を付けていってほしいですね。
--磯部さんは先輩として後輩たちにどうしても伝えたいことがあるそうですね。
磯部氏:そうなんです。この講義を、できれば1年生や2年生といった早い段階で受けることを強く勧めたいです。かつての私も学生時代そうだったように、せっかく芸術大学に入ったのだから、自分が好きなこと・やりたいことだけに没頭したいと考える人が多いと思うのですが、3年生や4年生になって就職を現実的に考え始める前にこそ、たとえ今は興味がなくても早く学んでおく価値があると思います。
こうした講義を通じて視野を広げ、アートとビジネスの絶妙なバランスを身に付けておくことは一生モノの強みになるはず。私は本当に今の学生さんたちがうらやましいです(笑)。
--最後に、皆さんから受験生・保護者へメッセージをお願いします。
藤本氏:感性は無限大です。芸術大学の4年間で育まれる感性や美意識は、将来社会で必ず生かされます。繰り返しになりますが、これからの時代は芸術大学への期待はますます高まるでしょう。「芸術では食べていけない」と感じているなら、今こそその思い込みをアップデートしてほしい。そして、名古屋芸術大学で、これからの社会でもっとも活躍できる、アートとビジネスを両立した稀少な人材になってください。
磯部氏:藤本さんのお話にあった、アーティストの感性や美意識がビジネスで評価されるという事実は、まだ一般的には十分に知られていないかもしれません。ですが、名古屋芸術大学では自分の得意なことを生かしながら経済的に自立し、活躍するための十分なスキルを身に付けることができますので、むしろお子さんが芸大に行くことを積極的に応援してあげてほしいと思います。
中川教授:芸大というと「社会で通用しないのではないか」という不安を抱かれがちなのですが、決してそんなことはありません。むしろ昨今は、多様性を重視する企業が増え、アートを専門に学んできた人材は大いに期待されています。現在でも名古屋芸術大学の学生は、多くの企業から、その感性や美意識だけでなく、幼い頃から継続して努力を重ねることで身に付けた粘り強さや諦めない心、やり抜く力といった非認知スキルも高く評価されています。
10年前と比べても求人数は大幅に増加し、2024年度は学生1人あたり69件の求人があるほど信頼が厚いです。4年間アートに没頭して培われた感性と、今回始動したプログラムによってビジネス知識を兼ね備えた人材がチームに加われば、間違いなく面白い化学反応が生まれるでしょう。
特に名古屋はトヨタをはじめとする日本を支える産業が集積する地域です。この地で、名古屋芸術大学の「アート」と「起業家育成」の融合によって育つ人材が活躍の場を広げていけば、まだまだ日本は新しい価値を創り出していけるのではないでしょうか。ぜひ1度キャンパスに来て、この最先端の教育を体感してみてください。
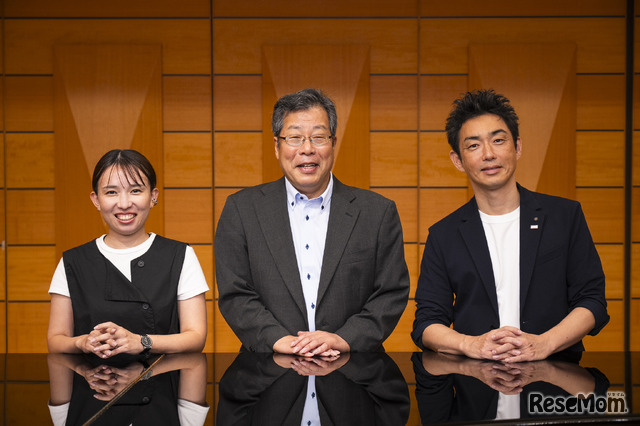
--本日は貴重なお話をありがとうございました。
名古屋芸術大学「起業家育成」プログラム 詳細はこちら名古屋芸術大学の「起業家育成」プログラムは、アートを学ぶ学生が社会で直面するさまざまな課題に対し、具体的なビジネススキルとマインドセットを提供するものだ。これにより、学生は自身の芸術性を追求しつつ、実社会で自立し、さらにはビジネスの最前線で活躍できる「二刀流」の無敵な人材となることが期待される。保護者にとっては、わが子がアートの道を進んでいくうえで安心材料となるだけでなく、未来の可能性を大きく広げる教育プログラムと言えるだろう。








