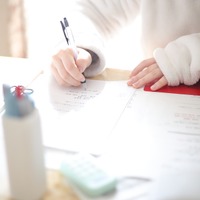受験者数が高止まりのまま推移し、引き続き高い関心と熱気に包まれた2025年の中学受験。今年の受験にはどのような傾向や変化が見られたのだろうか。
進学個別指導塾TOMASの副局長・教務本部責任者の松井誠氏に、1都3県の2025年度入試の振り返りだけでなく、「サンデーショック」の影響や思考力や表現力・記述力が問われる最難関中入試の傾向など、2026年度以降の入試の行方についても解説いただいた。2026年度以降の中学受験に挑戦するご家庭において、今から準備しておくべきこととは。
受験者数は微減ながらも厳しい状況
--まず、2025年の中学入試を振り返り、概況についてお聞かせください。
東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県の受験者数は5万2,300人、昨年比マイナス100人でした。小6人口が減少する中で、受験者数は100人しか減らなかったということになります。2月1日午前に限ってみても、小6人口に対する私立中学受験率は15.2%(森上教育研究所調べ)と過去最高だった2024年と同等でした。今年度も引き続き厳しい入試だったことは間違いありません。
今後も、同様の厳しい状況が続くと予想しています。これまで児童数が増え続けてきた東京では、文部科学省が2024年12月18日に公表した「令和6年学校基本調査」によると、2025年度の小3(2028年に小6)は10万2879人で、前年比でマイナス2,392人となりますが、一方で、日本の高水準の教育を子供に受けさせたいと考え、中国など海外から来日する家庭も増えてきていますし、県外からの流入もあります。引き続き予断は許さないといったところでしょう。

--難関校の志望動向はいかがでしたか。松井先生が注目する学校についても教えてください。
地域ごとにお話しましょう。
まずは東京です。最難関校を敬遠する傾向は模試の時期から見られましたが、本番でも男女御三家はすべて微減となりました。その次の層にあたる学校の人気が上昇していることも重なり、確実に安全志向が働いたとみています。また、渋谷教育学園渋谷、広尾学園などのグローバル教育に力を入れている共学校は引き続き高倍率です。これらの学校は進学実績も高水準で、今後も注目の学校です。
神奈川は男子御三家の聖光学院、栄光学園、浅野はいずれも東大合格実績、現役合格率とも素晴らしく、神奈川の受験生の選択肢を増やしています。一方の横浜女子御三家のフェリス女学院、横浜雙葉、横浜共立学園の3校は、共学校人気に押されてやや苦戦しています。そんな中、洗足学園は今年、東大合格者28名を輩出し、完全に神奈川女子校トップに躍り出ました。また、慶應普通部が昨年比130%と志願者数を伸ばしたことも今年のトピックスと言えるでしょう。慶應普通部の躍進は、合格最低点の開示など情報公開で入試が透明化されたことも影響していると思われます。
続いて、埼玉です。東京や千葉からも多数の受験生を集める埼玉ですが、今年は開智、開智所沢、開智未来が注目を浴びました。1回の入試で開智学園グループの複数校の合否判定を得られるため、受験者も増えています。また、昨年「医進コース」を設置した淑徳与野も受験者数を伸ばしました。埼玉は東京からのアクセスが良い学校が多く、埼玉の私学に目を向ける人が多くなった表れと考えています。
一方で千葉は、アクセス面では埼玉に劣りますが、「合格したら進学する」という志望度の高い学校が多いのが特徴です。2025年度の東大合格者75名の渋谷教育学園幕張、医学部医学科の合格率が全国トップレベルの東邦大学付属東邦、さらに2024年度に過去最高の東大合格者を出した市川の千葉御三家の進学実績が素晴らしく、入ったら後悔しない学校だと言えるでしょう。それ以外でも、麗澤、専修大学松戸、昭和学院など高倍率の人気校が多数あります。
全体的に、(1)高い合格実績、(2)スピーディな情報発信、(3)海外留学や語学教育などの国際教育に熱心、(4)面倒見が良いという特徴をもつ学校が伸びた印象があります。
2026年度入試、サンデーショックの影響は?
--2026年は2月1日が日曜日であることから、日曜日にミサを実施するミッション系の学校の一部が入試日程を移動する動きがあります。志望校選びにも影響が出てくることから「サンデーショック」の年と言われていますね。
サンデーショックはおもに女子の学校選びに影響します。女子学院、東洋英和女学院、立教女学院は、例年2月1日に実施する入試日を2日に移動します。これにより、桜蔭と女子学院、雙葉と女子学院などの併願が可能になり、最上位生にとっては大チャンスです。
以前は、女子学院を受けるお子さんの8割ほどが桜蔭も受験するというのが相場で、最上位層は桜蔭と女子学院、あるいは雙葉と女子学院を受験し、両校とも合格する生徒が多数いました。しかし、近年は志望校の選択肢が広がり、校風や卒業生の進学先など女子学院との親和性を考えると、早稲田実業や、国際教育に力を入れている渋谷教育学園渋谷や広尾学園などを選択する受験生も増えるのではないかと予想しています。
東洋英和女学院、立教女学院の伝統女子校が2日に移動することにより、同じ伝統校の学習院女子中等科、日本女子大附属中との併願も可能となります。しかし、女子大の人気低下などによりかつてほど王道の併願パターンとはなりにくく、先ほども出た広尾学園など共学校との併願が増えるかもしれません。
神奈川に目を転じると、フェリス女学院、横浜雙葉は日程を変更せず2月1日に入試を行うことを公表しています。一方、横浜共立学園は2日に移動。横浜女子御三家は、交通網の発達により渋谷教育学園渋谷などの東京の共学校や、洗足学園や豊島岡女子学園といった進学実績の良い女子校に受験生を奪われている状況にありますので、動向に要注目です。
前回のサンデーショックは2015年でしたが、当時と比べると学校の選択肢は格段に増えています。午後入試も浸透していますから、「ショック」というほどの影響はなく、受験生も過度に恐れることはないと思います。
男子は例年、合格実績を伸ばした学校が志願者を増やします。東京大学合格82名と巻き返した麻布中、昨年に続いて高い現役合格率を上げた聖光学院、東京大学合格者数過去最高を更新した浅野などは、2026年も大注目です。
また、コース制を一本化し午後入試で算数理科の二教科入試を導入するなど、改革に余念がない東京都市大付属、サイエンスセンター建設など理系に強い海城中、なども引き続き人気を集めるでしょう。
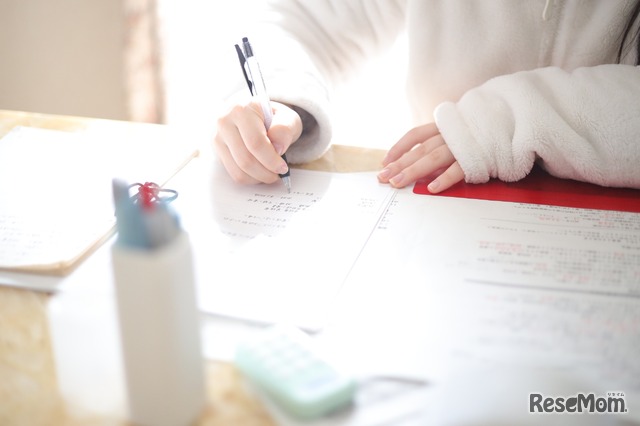
頻出分野、解答形式、解くスピード…その子に合った志望校選びを
--昨今の難関校における出題傾向はいかがでしょうか。
中学入試ではどの学校でも、その学校のレベルでの「基礎力」を問う問題が7割から8割を占めますが、出題形式、解答形式、入試時間、配点などは学校によってさまざまです。出題形式に慣れておかなければ、太刀打ちできない可能性もあります。
たとえば、2025年の麻布中学の算数は試験時間60分に対し設問は11問、1問に対し5.5分かかる計算になります。一方、女子学院中学は試験時間40分に対し設問は24問、平均1.6分で解かなければならない。同じ分野の問題でも1問にじっくり時間をかけて解くのと、塾で何度も解いたような典型的な問題を正確にスピーディに処理しているのとでは、求められる能力が違います。
そういった傾向への向き不向きも含めて併願パターンを組む必要があります。
--各校によって求められる力が異なるとのこと。だからこそ、その子の志望校に合った「難関突破力」を身に付ける必要がありますね。
子供の学力、素質、興味関心の方向は千差万別です。同じ算数でも、数の性質が苦手な子と図形が苦手な子では、優先順位が違ってきます。TOMASでは1対1の指導だからこそ、ひとりひとりに合った教材を見極めることが可能です。その子に合った指導法、進度、内容で進めることができるのがTOMASの強みです。
志望校選びという観点でも同様です。この学校は特徴的な問題が出るけれどこのお子さんには向いているとか、少し通学距離はあるけれどこのお子さんに向いている学校があるというように、それぞれのお子さんに合う個別の提案をすることができます。
合格の必須条件? 親に求められる「勉強熱心さ」とは
--家庭ではどういったことを心がければ良いでしょうか。
志望校への合格を叶えているご家庭は、概して親が協力的かつ勉強熱心です。親が受験に向けてしっかり準備して、学習の管理を計画的に行うのは絶対条件と言って良いでしょう。また、送り迎えや学校見学、オープンキャンパスや文化祭等のイベントに連れて行くこと、膨大な教材の整理など、家族の中での協力体制をしっかり作ることが重要です。
「中学受験は親7割、子供3割」という方もいますが、私は「子供が10割」だと思っています。ただし、その「子供の10割」を引き出すのが親と塾の仕事だと思うのです。
子供の受験に伴走をしていると、多かれ少なかれどの保護者にも、感情的になってしまう瞬間が訪れます。自分の感情を常にコントロールして、子供と向き合うのは難しいことです。ですので、ぜひお通いの塾の先生や我々のような第三者に相談し、戦略を練っていってほしいと思います。
--「頼れる第三者を見つける」というのも、親に課された重要な仕事ですね。
ご家庭に合った塾を見つけることは、親にとっての心のよりどころを見つけることにもつながります。受験勉強に取り組む10歳から12歳の子供は、成長真っ盛り。大人びているときもありますが、まだまだ子供っぽいときもあります。そういう難しい年代のお子さんと向き合う中で出てくる悩みを、親だけで背負うのは大変です。
わが子の受験というセンシティブな話題だからこそ、普段付き合っているママ友にも話せず閉塞感を感じる、というのも中学受験渦中のご家庭の悩みとしてよく聞きます。フラットで視点で、専門的なアドバイスを冷静に伝えてくれる。それができるのは、塾しかないと思うのです。「塾の先生にこんなことを聞いて良いかな」とか、「こんな質問をしたら先生に笑われるんじゃないかな」と戸惑っている保護者の方もいらっしゃるかもしれませんが、遠慮は要りません。ぜひ、塾を使い倒す気持ちで利用していただきたいです。
--難関中を目指すには、やはり低学年にスタートを切るほうが良いのでしょうか。
必要性を感じたら、なるべく早いタイミングで始める、これが鉄則ではないでしょうか。たとえば10歳からピアノやバレエを始めて、そこからプロを目指す子はいませんよね。それと同じで、能力がある、あるいは能力を伸ばす必要がある子と感じたら、すぐその素質を伸ばすような教育をしてあげるほうが、良い結果が導ける可能性が高いと思うのです。
ただし、それは必ずしも塾に入って勉強することを推奨しているのではありません。本を読ませる、あるいは好きなことを調べさせるなど、子供の知的好奇心に保護者がしっかり向き合うということです。精神的に幼い、集中力が続かないというようなお子さんもいらっしゃいます。その場合は、本人の能力以上のものを与えて鍛えようとするのではなく、その子の成長をじっと待つことも必要です。
小6になった途端、長時間机の前に座って勉強できるようになるかと言ったら、決してそうではありません。長い時間をかけて学習習慣を付けたり、好奇心の土台をつくっておくからこそ、晴れて12歳で受験勉強に向かう力が発揮できるようになるのです。

非受験学年こそ、積極的に情報収集を
--先ほど「勉強熱心さが合格への鍵」というお話がありました。低学年の親が中学受験について学ぶ機会はありますか。
たとえば、2025年度も実施する「学校見学説明会」も、保護者にとって有効な学びの場を言えるでしょう。「学校主催の説明会はすぐに満員になり、申し込めない」「合同説明会では参加者数が多くてじっくり質問できない」という声を受け、TOMASが有名中高一貫校の協力を得て、独自に開催するイベントです。5月から10月にかけて、各学校やTOMASの校舎を会場に開催されます。お子さんの学年問わず参加できますので、低学年のご家庭も積極的にご参加ください。
親がどれだけ学校のことを調べるかは重要なポイントです。中学校・高等学校は、お子さんが10代の多感な時期を過ごす場所なのですから、足を運び、しっかりと見て、感じ取ってきていただきたいですね。
低学年のうちから多くのイベントに参加し、先々を見据えてわが子の中学受験について勉強している保護者は、子供に期待をかけすぎることがなく、現状と目標のバランスがよく取れているように感じます。ぜひ、いろいろなイベントに参加して保護者の方にも勉強していただきたいと思います。
--受験を検討しているご家庭にメッセージをお願いします。
子供と保護者が目標に向けて一生懸命勉強するのはとても素晴らしいことです。お子さんと一緒に、楽しんでいただきたいと思います。大変なことももちろんあるでしょうし、志望校とは異なる学校に進学することもあるでしょう。それでも、子供が一生懸命勉強し、厳しい競争の世界で挑戦したこと自体が素晴らしいことだと思います。
日々成長するお子さんを、温かく見守って応援してあげてほしいです。そして、保護者の方も不安になって負の感情をぶつけたくなったら、ぜひTOMASにご相談ください。プロがアドバイスいたします。
--ありがとうございました。
私立中学への人気が高まる中で、受験の形式や求められる力は日々変化している。だからこそ、保護者も正しい情報をしっかりと集めておくことが重要だ。また、家庭だけで悩みを抱え込まず、子供ひとりひとりの長所を伸ばしてくれる塾を、親にとっても安心して頼れる場所として、うまく活用していきたい。
TOMAS主催「学校見学説明会2025」の詳細はこちら