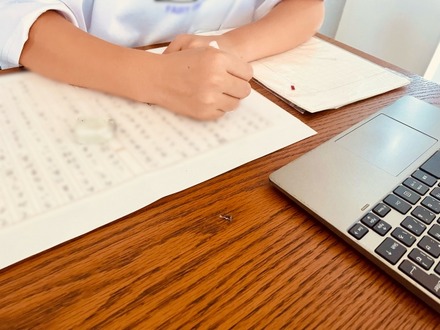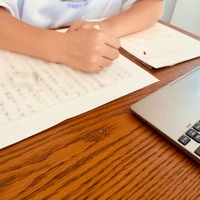夏休みの宿題の手強い相手「読書感想文」。最終日まで残ってしまう筆頭でありながら、1日やそこらでは終わらない骨太な実力をも兼ね備える強敵だ。ある書物について感じたことを400字~1,000字程度でまとめるのは、大人ですらも難しい。
だが、宿題が終わらなければ胸を張って登校できないだろう。そこで、今回は読書感想文が簡単に書ける「読書感想文のやっつけ方」を、ステップごとに解説していく。2日以内に終わる想定なので、8月末になっても十分間に合う。どうか強大な宿題の前に諦めるのではなく、効果的な武器をもって立ち向かってほしい。
STEP1:本を決める
まずは題材となる本を決めよう。課題図書が指定されている場合はそれを読めばいいのだが、そうでない場合には、自分で本を選ぶ必要が出てくる。どうしても思いつかない場合は、インターネットで「小学(中学)〇年生 読書感想文 本」と調べると候補が見つかるだろう。以下に年代ごとの課題図書候補をいくつかあげてみたので、参考にしてみてほしい。
中編(小学校3~4年生むけ)
『エルマーのぼうけん』(ルース・スタイルス・ガネット 著)
これは、少年の父・エルマーが若かったころのお話。エルマーが9歳の頃のこと、ある雨の夜に年をとった野良猫から「どうぶつ島」に捕らえられているかわいそうな竜の話を聞いたエルマー。空の低いところに浮いていた雲から落っこちてきた、小さな子どもの竜で、ジャングルの猛獣のために川を作らされているのだそう。矢も楯もたまらず、彼は竜を助けに冒険の旅へ出る。リュックサックには「チューインガム、ももいろのぼうつきキャンデー2ダース、輪ゴムひとはこ……」などたくさんの道具が。はたして、エルマーの冒険はうまくいくのだろうか?
『やらなくてもいい宿題』(結城真一郎 著)
算数が得意な数斗はクラスでも一番の天才少年。だが、ある日やってきた転校生・ナイトウさんは、不思議な雰囲気をまとっていた。転校生は数斗へ様々な問題を出題し、数斗はそれをあっけもなく解き進めるが、実は問題には罠が仕掛けられていた……。ナイトウさんの正体、そして目的は何なのか? 『#真相をお話しいたします』の著者が送り出す児童書ミステリー!
長編(小学校5、6年生むけ)
『はてしない物語』(ミヒャエル・エンデ 著)
『モモ』のミヒャエル・エンデが手掛ける児童書ファンタジーの傑作。読書と空想が大好きな主人公・バスチアンは、ちょっとおデブな体型などを理由にクラスでいじめられていた。さらに、母を失ってからは父親や家庭にも距離を取っており、帰る場所を失ってしまった。ある日、いじめっ子から逃げ込んだ先で、バスチアンは不思議な本を見つける。あかがね色の布でなされた見事な装丁に、表紙にしつらえられた尾をかみ合って円をなす2匹の蛇。そのタイトルは『はてしない物語』といった__。実物の『はてしない物語』と作中の『はてしない物語』とがリンクしながら進んでいくストーリーからは、現実と空想の境目をいやおうなしに意識させられる重厚な読書体験が得られる。
『ぼくらの七日間戦争』(宗田理 著 角川つばさ文庫)
明日から夏休み! 胸を膨らませるクラスメートのさなか、東京下町にある中学校の1年2組の男子たちが忽然と姿を消した。事故にあった? 誘拐事件に巻き込まれた? 様々な憶測を巡らせる中で、男子たちはある廃工場に立てこもっていることが判明。なんと彼らは、廃工場を拠点として、大人に反抗する解放戦争を計画していた! 夏の青空のようなカラッとした爽やかなストーリーを楽しめる、一大エンターテイメント作品。
ステップ2:本を読む
次に本を読んでいく。この時、印象に残ったシーンのページに付せんを挟んでおこう。付せんには、その時感じた思いをなるべく具体的に書いておく。そうすれば、読み終わった後に「こんなシーンがあったな、こう感じたな」と鮮明に思い出すことができる。
付せんの数だが、多くて困ることはないだろう。逆に少ないと書く時の内容出しに困ってしまうので、少なくとも4か所~5か所は付せんを貼れるようにする。10か所でも20か所でも問題はない。これが、「こんなシーンでこんなことを考えた」と書く時の材料になるのであり、少なすぎる材料のやりくりに頭を悩ませるよりも、多すぎる材料の捨てる場所を選ぶほうが簡単だからだ。
ステップ3:パソコンで下書きする
次は実際に文字を書いていく。直接原稿用紙に書くのではなく、パソコンでWordやメモ帳を立ち上げて、そこに下書きをする。パソコンで一度書き出すのは難しい作業かもしれないが、幼少期からパソコンのキーボードに慣れておくことは、高校や大学での学び、それ以降の人生にて有利に働く。Wordならば文字カウント機能があるので、自分が何文字書いたのかすぐに確認できる。ちなみに、ブラインドタッチ(キーボードを見ずに入力する技術)は早く身に付けておいて損はない。ぜひ小さいころからキーボードやローマ字入力に慣れてほしい。
タイトルは最後に決める。なので、最初は空欄か、「『〇〇』を読んで」程度の仮タイトルで良い。書き出しは「私は『〇〇』を読んで、△△な物語だと感じました」と結論を述べる。そのあとは、「物語の中で、☆☆というシーンがあるのですが、私はここを読んで△△だと感じたのです」と続ければ良い。
この後は文章の展開の方向によるが、たとえば思い出から具体例を出すのも面白い。「私は、このシーンに見覚えがありました。以前、□□に遊びに行った時のことですが~」と、自分の思い出語りを挿入するのだ。自分の話に持ち込めさえすれば、後は何を書いても自由になるので、かなり書けることの幅が広がる。
西岡壱誠著『東大作文』(東洋経済新報社)では、作文を書く際の「4つの主張の型」が紹介されている。これは、「最終的に何が言いたいか」を軸に大別した文章のスタイルで、どのような内容を書きたいか目標を立てるときに、役に立つだろう。
伝えたいことの種類によって、作文の主張には大きく分けて4つの型がある。どの型を使うかを意識することで、自分の考えをよりはっきりと、わかりやすく書けるようになる。
作文を書きやすくなる「4つの主張の型」
①感情型ー自分が感じたことを伝えたい …自分の気持ちを軸に、感動や驚き、共感などを言葉にする型
例:この本を読んで、自分だったら同じようにできただろうかと考え、胸が熱くなりました。
②共有型ー相手に情報を届けたい …客観的な出来事や情報を伝える型
例:主人公の友人が「人を信じることは怖いけど、信じなければ前に進めない」と言っていました。
③要望型ー相手に伝えたいお願いがある …自分が感じたことをもとに、相手に対して主観的な願いを伝える型
例:この本を読んで、もっと多くの人が自分の気持ちに正直になれる世の中になってほしいと思いました。
④警鐘型ー気づいていない問題を知らせたい・意識を変えたい …客観的な事実に基づき、相手の行動や意識を変えたいときに伝える型
例:私たちも、主人公のように他人のために勇気を出す姿勢をもっと大切にするべきだと思いました。
おそらく、多くの人は感情型、あるいは要望型になるだろうが、何か学びを得られたならば共有型などにしても、面白い作文が書けるかもしれない。
ステップ4:ChatGPTに推敲してもらう
ひととおり文章が書けたら、全文をコピーして、ChatGPTのチャット欄にペーストする。AIに日本語文法を添削してもらえれば、作文に不安がある子でもまとまった文章を書くことができる。
この時のプロンプト(命令文)は
「以下は小学(中学)〇年生による読書感想文です。あなたは国語の教師として、この感想文について添削してください。その際は、何が悪くて、どのように直せば良いかポイントごとにまとめて明記してください。」
として、1、2行空けてから自分の文章を貼り付ける。
場合によっては、推敲すると原稿用紙をはみ出すほど文字数がかさんでしまうかもしれない。その時は、再度内容を練り直す。AIに「〇〇文字以下になるように推敲のアイデアを示して」と頼んでみるのも良い。そして、新しく原稿ができたら、再度提出して添削してもらう。これを「規定字数を突破した添削済みの文章」が出力されるまで繰り返す。

ステップ5:清書する
推敲が終わったら、いよいよこれを原稿用紙に書き写す。書き写しミスや字の間違いなどには気を付ける。また、あまりにも字が下手だと採点対象外になる可能性があるので、ある程度無理なく読める範囲のきれいな字を意識して書く。
いかがだっただろうか。ここで紹介したステップは、本の選定から読破までを1日、実際に感想文を書くので1日と、最短で全2日間での完遂を想定している。長編小説であればもう少しかかるかもしれないので、できれば夏休みが終わる10日前には読み始めておくと安心だろう。
小中学生の読書感想文であれば、400文字から1,000文字程度であろうから、作文に不慣れであっても3~5時間程度もあれば文章は書きあがると考えられる。そこから文章の推敲を行って、書き写すことを考えても、2日あれば終わる。AIの力を借りれば、日本語の間違いなどを学ぶこともできるため、さらに色濃い学びが得られること間違いなしだ。
ここで紹介した方法をもって、無理なく読書感想文の宿題を終わらせてほしい。