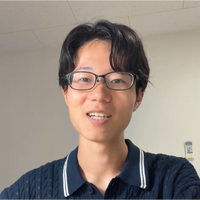あえて地元を離れ、遠方の大学に行きたい。でも、志望校対策のノウハウがない、慣れない土地でのひとり暮らしは不安…。そんな迷いがある受験生や保護者に向けて、東北大・京大・同志社大に「越境」した駿台予備学校の卒業生3名にリアルな体験談を語ってもらった。
<インタビュイー>
稲垣 俊輔さん: 大阪府出身/東北大学工学部1年生/駿台予備学校・大阪校
梶原 遥さん: 広島県出身/京都大学法学部1年生/同・広島校
野見山 詩織さん: 福岡県出身/同志社大学社会学部1年生/同・福岡校
地元にも大学があるのに、なぜ「越境」したいと思ったのか
--皆さんそれぞれ自宅から通えるところにも良い大学があるのに、なぜあえて地元を離れる選択をしたのか、その理由からお聞かせいただけますか。
稲垣さん:最初は僕も自宅から近い大阪大学を目指そうと考えていました。まわりに志望する人が多く、身近な選択肢だったのですが、高3の夏にもう1度自分の進路について考え直したとき、「自分が深く学びたいのは素材や材料の分野だ」と思ったのです。そこであらためて調べてみると、東北大学がこの分野に強いことがわかり、ここに行きたいと強く思うようになりました。また、実家暮らしで親に頼りっぱなしだったので、「1度大阪を出て自立したい」という思いもありました。
梶原さん: 僕は将来、法曹に進みたいと考えていて、法学部進んだ高校の先輩から話を聞いたり、ネットで調べたりした結果、将来の就職を考えると国立では東京大学、京都大学、一橋大学が強いことがわかりました。ただ、両親にとって子供は僕1人ではないので、関東圏だと家賃や帰省時の交通費など経済的な負担が大きくなると思い、京都大学を第一志望にしました。
野見山さん: 私の地元は福岡なので、近くには九州大学があります。けれど、私が学びたいと思っていた教育学と社会学を同時に学ぶには、同志社大学の社会学部教育文化学科が理想の環境でした。また、稲垣さんと同じく、九州を離れて京都でひとり暮らしをしてみたいという強い憧れもありました。
--とはいえ、まだ高校を出たばかりの18歳。知らない土地でのひとり暮らしに不安を感じませんでしたか。
稲垣さん: そうですね。正直なところ、かなり不安はありました。特に僕は、誰かと話をしていないと思考がネガティブに陥りがちなところもあって、知り合いがほとんどいない場所でのひとり暮らしは心が病むのではないかと心配でした。でも、東北大学の寮に入り、8人で水回りをシェアするユニットタイプの部屋だったので、共用スペースに行けば雑談する相手がいる環境にはすごく助けられました。ルームメイトにはインド人の留学生がいて、時々カレーのおすそ分けをもらうことも(笑)。東北大学は地元の人が意外と少なくて、自分と同じような境遇の人が多かったので、不安はほとんどなくなりました。
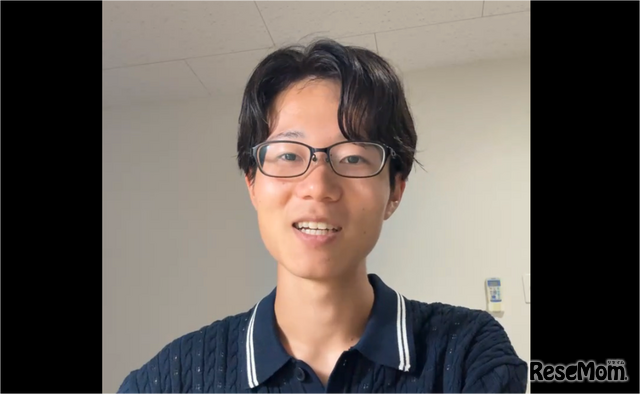
梶原さん: 僕も高校を卒業するまでは親に頼りきりだったので、ひとり暮らしに不安はありましたが、同時にワクワクする気持ちもありました。僕の住んでいるのは学生寮タイプのマンションで、食事付きなのでとても助かっています。また、食堂や大浴場など共用スペースで自然と人と顔を合わせる機会が多く、寂しいと感じることは少ないですね。京都大学も全国各地から学生が集まっていて、寮にも色々な出身地の人がいます。
野見山さん: 私は普通のアパートに住んでいるので、炊事洗濯などすべての家事を自分でやる必要があり、加えて大学の授業が始まると、わからないことを誰に聞けば良いかわからないという不安も大きかったです。でも、親に相談したり、同じように福岡から関西の大学に進学した友達と助け合ったりしながら、何とか乗り越えてきた感じです。
「越境」の受験は不利?周囲からの反対は…?
--地元ではない大学を受験するにあたり、不自由に感じたことや不利だと思ったことはありましたか。
梶原さん: 広島の学校では広島大学対策は充実しているのですが、僕が志望する京都大学に特化した対策は、どうしても講座の数が限られてしまいます。そのため、オンライン授業に頼ることも多かったです。
野見山さん: 同感です。私の地元でも、九州大学の対策講座は充実しているものの、それ以外だと物足りなさを感じざるを得ませんでした。また、国公立大志向が根強いので、地元以外の私立大学を目指す人は多くなく、個別試験の対策が十分にできるのか不安でした。
稲垣さん: 僕は1浪で、浪人の時はAO入試にも出願したので、東北大学は合計で3回受験したことになります。その中で不利だと感じたのは、受験時のホテル住まいです。普段とは違う環境で、試験前につい夜遅くまで勉強してしまい、普段のルーティンを崩してしまったり、外食続きで体調管理が難しかったりしたこともありました。
--「なぜ地元に良い大学があるのに、遠くに行く必要があるの?」といった周りの大人の意見に対し、どのように向き合いましたか。
稲垣さん: 高3の夏に東北大学を受験したいと親に伝えた際には、きちんとその理由を説明するよう求められました。でも、東北大学だからこそ自分がやりたいことができると具体的に伝えると納得してくれました。
梶原さん: 父の実家が福岡にあるので、親からは「九州大学の方が安心だ」と言われたことはありました。ただ、僕自身としては、進路を考えた結果「京都大学しかない」という気持ちが強かったので、気持ちが揺らぐことはありませんでした。親は、そもそも僕に合格できる力があるのかという不安もあったようですが、最終的には僕の意志を尊重してくれました。
野見山さん: 私も当初は「九州大学ではダメなのか」と言われました。実家から通ってほしいという思いが強かったようで、九州大学以外にも、通える範囲にある大学をたびたび勧められました。でも、私はむしろそのたびに、「夢を必ず実現するぞ」という気持ちが大きくなっていったように思います。自分のやりたいことを総合的に考えた結果、この選択肢しかないのだと何度も説明し、最後は両親ともに納得して応援してくれたので、私は幸せだったと思います。
自分が今ここでできることを着実にやっていく
--志望校対策や情報収集、モチベーション維持はどのように行いましたか。
稲垣さん: AO入試対策として、駿台の合格者による入試レポートは、面接のようすや質問内容が詳しく載っていて、とても貴重な情報源でした。一般入試対策では、大阪校の難関国公立大コースに在籍したので、東北大学の対策講座は映像で受講しながら、過去問を使って頻出内容を調べ、そこを重点的に取り組みました。
AO入試は情報が少ないので、対策をするうえでは論文を読むなど、いろいろと時間をかけて調べる必要があったのですが、その過程で「どうしても東北大学に行きたい」というモチベーションが高まったように思います。また、夏にオープンキャンパスに参加し、現地で大学の雰囲気や研究内容を直接見たことも大きかったですね。
梶原さん: 過去問は赤本を使って、学校の先生に添削をしてもらいました。また、高3からは駿台の講習で京都大学の対策に特化した授業を受けました。これは対面の授業だったので、直接講師の先生に質問することができ、京都大学の出題傾向を踏まえたアドバイスをたくさんしていただいたので、かなり力が付いたと思います。周りには京都大学を含め、難関の国立大学を目指す友達がいたので、お互いに励まし合いながらモチベーションを保つことができました。
野見山さん: 私は志望校に進学した先輩に勉強法を詳しく聞き、過去問を解いて弱点をあぶり出し、ひとつずつ補強していくことで力を付けていきました。周りには地元から離れた私立大学を目指す人が少なかったので、モチベーションの維持は大変でしたが、親に不安な気持ちを打ち明け、励ましてもらうことで乗り越えられました。

「越境」×「自立」が大きな成長を促す
--今はどんな学生生活を送っていますか。ひとり暮らしを始めてみて想像と違ったことはありますか。
稲垣さん: 今は陸上部に所属し、授業→部活→自炊というルーティンの生活です。理系なので常に課題があり、勉強は結構忙しいのですが、後期からは実験も始まるのでもっと忙しくなりそうです。
ひとり暮らしを始めて大変なのは自炊です。作りおきをしているのですが、部活で疲れて帰ってきたときに作りおきがなくなっていると絶望的な気持ちになります(笑)。外食すると出費がかさむのでなるべく避けたいのですが、時間のやりくりが思った以上に難しいですね。
梶原さん: 僕は寮で朝食の時間が決まっているので、結構規則正しく生活できています。授業に出た後はサークルやバイトがあり、課題があれば帰宅後に取り組んでいます。ひとり暮らしを始めてみて、圧倒的に自分の時間が増えましたね。僕は法曹を目指しているので、後期からはもう少し勉強の割合を増やしていきたいと思っています。
野見山さん: 私は授業が多い日は大学がメインですが、少ない日はサークルの他、中学校で学生ボランティアとして、生徒たちの勉強を見たり部活動を手伝ったりしています。また、レストランでホールのアルバイトもしているのですが、京都は外国人観光客が多いので、接客を通じて英語力が上がっている実感があります。ひとり暮らしで特に大変なのは、お皿洗い(笑)。つくづく親のありがたみを感じています。
--実家を離れて、どんなところが成長したと思いますか。
稲垣さん:自分のことを誰も知らない土地では、自分から動かないと何も起こらないということを実感しました。実家にいた時は、待っていれば誰かがやってくれるような感覚でしたが、こちらに来てからは主体的になったように思います。また、作りおきで料理の腕が少しは上がった気がします(笑)。
梶原さん: 僕は、自己管理能力が高まりました。実家にいるときは、朝起こしてもらったり、忘れていることがあってもリマインドしてもらったり、何かと親に頼っていたなと思います。お金の管理についても、ひとり暮らしでは仕送りとバイト代を合算し、自分で予算を立てて生活する必要があるので、水筒を持ち歩くなど、無駄遣いを減らす努力もできるようになりました。

野見山さん: 私は、親や周りの人たちへの感謝の気持ちをちゃんと言葉で伝えられるようになったのがいちばん大きな成長だと感じています。ひとり暮らしを始めて、料理や掃除、洗濯など、誰かにやってもらって当たり前だと思っていたことに気付き、どれほどの労力と時間がかかるのかを痛感し、素直に「ありがとう」と伝えられるようになりました。
遠いという理由だけで夢をあきらめないでほしい
--地元を離れることへ不安を感じている受験生や保護者に向けて、どんな魅力や成長機会があると伝えたいですか。遠方の大学進学を諦めないために、どのような気持ちで受験に臨めば良いでしょうか。
稲垣さん:「案ずるより産むが易し」で、自分でなんとかしないといけない状況に置かれれば、意外となんとかなるものです。また、自分で決めて地元を出てきたという覚悟が自立する能力を育て、大きく成長させてくれると思います。
受験直前はネガティブな思考に陥ってしまうことがあると思いますが、僕はそんなときに駿台の学習コーチから、「うまくいかない未来を想像するのではなく、うまくいった後どうするのかを常に考えなさい」と言われた言葉が心の支えになりました。ネガティブな感情は溜め込まず、親や先生など、周りの人に頼りながら頑張ってほしいです。
梶原さん: 大学に入ると同じように地元を離れてやってきた仲間がたくさんいるので、過度に心配しなくても大丈夫です。これまで生きてきたコミュニティを出て、まったく新しい環境に身を置くことで、多くの新しい出会いと発見があります。こうしたさまざまな人との出会いと新しい気付きが視野を大きく広げてくれますし、親の保護下にあるコンフォートゾーンから自分の将来に向けた自立こそ、さらなる成長を促すのだと思います。
行きたい大学が実家から遠いからという理由だけで、夢をあきらめるようなことはしてほしくありません。「自分の夢を実現するために行きたい大学に行くんだ」という強い意志をもって努力することが、受験勉強のモチベーションにもつながるのではないでしょうか。
野見山さん: 私がいちばん伝えたいのは、地元を離れてもひとりになるわけじゃないということ。そして、今2人が言ったように、ひとり暮らしで遠方から来ている仲間が大学にはたくさんいるので、「人にどんどん頼っていいんだよ」ということも忘れないでほしいです。頼ったり頼られたりを繰り返す中で人間関係が深まり、かけがえのないつながりが得られるのだと思います。
「実家から遠いと自分には無理かもしれない」と不安に思うことがあっても、誰かに話せば心が軽くなることはたくさんあります。遠慮せずにいろんな人に頼って、自分の夢をどう叶えるか、ポジティブにその方法を考えることで、進み続けてほしいですね。
--ありがとうございました。
地元を離れ、越境した慣れない環境で、家族や友達を頼りながら不安を乗り越え、成長を実感しているようすからは、前だけを向き、希望に満ちていると感じた。遠方の大学への進学を考えている受験生やその保護者は、一旦その不安を横に置き、そこで学びたいと感じる気持ちをもっと大事にしてみても良いのかもしれない。
第一志望は、ゆずれない。「駿台予備学校」の詳細はこちら