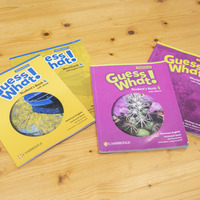かねてから高いレベルの英語教育で注目されている埼玉県川越市の星野学園小学校。2025年度からケンブリッジ英語教材を導入し、小学1年生から完全オールイングリッシュでの授業を展開している。導入から3か月、「子供たちの英語への取組み方が劇的に変化した」という星野学園小学校のようすを見に、取材に伺った。
星野学園小学校は、埼玉県内では東武東上線沿線初の私立小学校として2007年に開校し、来年で創立20周年を迎える。同校の英語教育は、単なる語学習得にとどまらない。「英語を学ぶ」のではなく「英語で学ぶ」。その革新的な取組みの秘密を探るべく、同校教頭の河辺秀幸氏、教務主任の本松敬司氏、英語担当の佐藤優氏、生徒指導主任の山田奈穂美氏、そして星野学園理事長であり、同校校長でもある星野誠氏に話を聞いた。
【プロフィール】
星野誠先生:星野学園理事長、星野学園小学校・中学校校長
河辺秀幸先生:星野学園小学校 教頭
本松敬司先生:星野学園小学校 教務主任
佐藤優先生:星野学園小学校 英語担当教諭
山田奈穂美先生:星野学園小学校 生徒指導主任
「勉強の仕方を学ぶ」小学校時期の基礎教育
--小学校設立の背景と当時の思いを、振り返ってお聞かせください。
星野氏:星野学園は高校から始まった学園ですが、長いこと「いつか小学校を作りたい」と考えていました。そこには、12年間で責任をもって子供を育てていきたいという思いがありました。

河辺氏:星野学園が大事にしている教養教育を、もっと小さいころから学び、身に付けてほしいという思いから2007年に開校したのが、この星野学園小学校です。
--小学校の時期というのは、その後の人生の基礎ともいうべきものだと思います。特に学習面について、星野学園小学校では何を大切にし、どのようにして子供たちの力を伸ばしているのでしょうか。
河辺氏:学習面で特に大切にしていることは、子供自身が自主的に楽しんで学んでいくことです。大人からやりなさいと言われ「やらされている勉強」というのは、身に付きづらいものです。自ら学ぶという姿勢を身に付けるためにも、始業式や終業式などの節目には、校長から子供たちに「小学校で勉強の仕方を学び、皆さんにはぜひ生涯にわたって学び続けてほしい」と話しています。
授業を行う際に大切にしているのは、基礎基本を重視し、子供たちに「できる」「わかる」と実感して、自己肯定感を高めてもらうことです。また、一方通行の授業ではなく、子供たちからの意見や疑問に対して私たち教師もしっかりと受け止めて向き合う、双方向の授業をとても大切にしています 。
「英語を使って何をしたいか」を問い続ける教育
--星野学園小学校の教育の中で英語教育はどのように位置づけられますか。他の教科との関連性や、教科外の活動との関連性について教えてください。
河辺氏:本校では、教科での学びにとどまらず多彩な行事や活動を通して、子供たちは全人的な学びを得ます。そのため英語も、将来を見据えたときの選択肢のひとつとして学んでいくものとして捉えています。
本校の英語教育では、英語が話せるようになる、書けるようになることに主眼を置いていません。「英語を使って何をしたいか、将来何をやりたいのか」という目標意識をもったうえで、英語を勉強してほしいと考えています。
語学習得にとどまらず、英語をツールとして、学校での学びを通じて「できた」「わかった」という体験が増えることを期待しています。

--今年の春からケンブリッジ大学出版の英語教材を新たに導入されたと聞いています。採択にあたっての思いや背景などを教えてください。
佐藤氏:小中高の英語科の中で検討した結果、今年度からケンブリッジ大学出版の「Guess What! American English Updated(以下、Guess What!)」というテキストを導入しています。今回の教材導入は、英語のスキルを単に上げるためのものではありません。他の出版社のものも検討しましたが、批判的思考力であったり、想像力であったり、コミュニケーションを通してプロジェクト学習を行ったりという「英語を通して21世紀型スキルも学べる」という点に魅力を感じ、「Guess What!」の採用を決めました。
教材の導入に伴い、まず英語の授業をオールイングリッシュにしました 。授業自体を英語で進めるようになったことで、英語を使って物事を学ぶ環境を実現することができています。
--実際に導入してみて、子供たちの反応はいかがでしたか。
佐藤氏:子供たちの適応能力は、想像以上に高いですね。オールイングリッシュの環境に怯んでしまうかと思いきや、すぐに「英語の授業はこういうもの」と切り替えてくれました。導入からまだ3か月ですが、英語で発話する量が明らかに増えてきています。もちろん日本語で話しかけてくる場面も多いのですが、我々が英語で反応したり、「今の内容を英語でも言えるかな」と促したりすることで、子供たちも英語でコミュニケーションしようと挑戦してくれます。高学年の英語の授業では、日本語を耳にすることはほぼありません。

「英語で学ぶ」CLILの実践
--ケンブリッジ大学出版の「Guess What!」は、英語のスキル向上に限らず、総合的に学べる教材とのことですが、他教科との関連性について教えてください。
佐藤氏:ケンブリッジ大学出版の教材は「CLIL(Content and Language Integrated Learning)」、つまり英語で教科外の内容を学ぶ、英語で他教科を学ぶというアプローチが特徴的です。
「Guess What!」の中のコンテンツの一例を紹介しましょう。たとえば、アートについて学びます。まずは英語で芸術について触れ、それについてディスカッションなどを行います。最終的にはプロジェクト学習として、これまでの学びを生かしながら、実際に作品を制作します。3年生はコラージュ作品、6年生ではモザイクアートなど、内容もさまざまです。
アートのほかにも、地球儀を使って大陸名や国名を学ぶなど、社会科や理科と関連付くコンテンツも多くあり、既存の英語教材では見聞きしなかったような内容を、英語を通して学ぶことができます。子供たちの感覚では、「英語を」勉強しているというより、「英語で」勉強しているという感覚の方が圧倒的に強いと思います。
英語教育における6年間のステップアップカリキュラム
--英語教育の6年間のカリキュラムについて、詳しく教えてください。
佐藤氏:小学1~2年生は週に1時間ずつ、ネイティブ教員と英語科の教員のティームティーチングを実施しています。1年生では、まずカードやアクティビティを通して、英語の音と文字に慣れていくところから始めます。
1年生の2学期から「Guess What!」を使ったカリキュラムが本格的にスタートします。2年生までに1冊目の教材が終わるのですが、この段階ですでに英検5級レベルを超えることになります。
3、4年生になると、ネイティブ教員と日本人教員による週1時間の授業に加え、日本人教員が単独でおこなう授業が1時間増えます。日本人教員の授業でおもにインプットを行い、ネイティブ教員との授業で積極的にアウトプットしていくイメージです。
そして5、6年生になるとさらにもう1時間英語の授業が増え、週に3時間英語を学ぶ体制になります。6年生では本学園の中学校・高等学校から英語科の教員を招き、授業を行います。このような小中高接続カリキュラムをはじめ、小中高12年間を見通したうえで、それぞれの年齢に応じた英語教育を展開できるのは、本学園だからこそです。
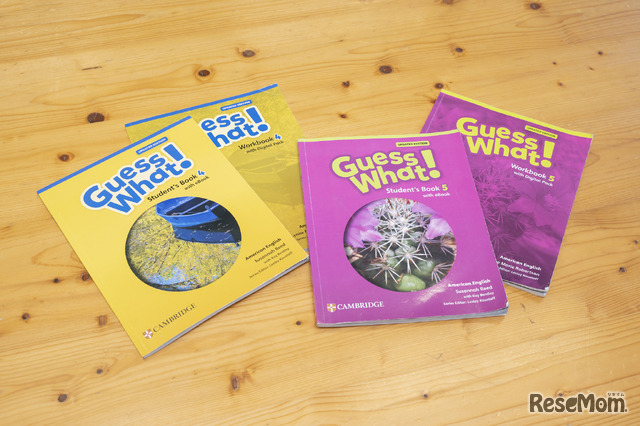
英語教育で大切にしている指導方針とは
--日々子供たちの英語教育にあたられる中で、特にこだわっていることを教えてください。
佐藤氏:本校の英語教育でいちばん大切にしているのは「チャレンジ」です。とにかく使ってみよう、英語で解決してみようという、そのチャレンジ精神を何より大切にしています。
たとえ拙い英語表現であっても、意図を汲み取ってあげて、「自分の発言が相手に伝わった」という体験につながるようにしてあげたい。「英語で理解してもらえた、英語が使えた」という成功体験を、できるだけ積みあげられるようにしています。
本松氏:日本語を習得するプロセス、具体的には一語文から始まって、語彙の数が増え、徐々に会話ができるようになっていくという流れを、子供たちは英語で再度体験することになります。少しずつで良いから、わかる単語を組み合わせて、会話を繰り返すうちに、徐々にコミュニケーションできるようになっていきます。
山田氏:私は他教科を担当していますが、佐藤先生の英語の授業を見ていて、驚きました。たとえば、国語ではそれまで自分の意見を表現するのが苦手そうだと感じていた子が、佐藤先生の授業では意欲的に手を挙げて、堂々と発表をしている姿を目にしたんです。英語の授業では、日本語の授業とはまた違う子供たちの良さが引き出されるんだなと感心しました。

ニュージーランド修学旅行での実践体験
--チャレンジ精神を大切にした英語教育、その実践の場として、ニュージーランド修学旅行がありますね。
本松氏:おっしゃる通り、5年生のニュージーランド修学旅行は、まさにこのチャレンジ精神を発揮する場です。コロナ禍はやむなく中止していましたが、今年度6年ぶりに再開されます。
子供たちからは「英語を話せなきゃダメですか」とか、「どのくらいの英語力がないといけませんか」という相談がありますが、英語のレベルは二の次、三の次です。この修学旅行の目指すところは、小学生という年齢で異文化の方と交流する海外経験をすること。この体験を通して視野を広げることが、もっとも大切だと考えています。
河辺氏:修学旅行のメインは、ファームステイと学校交流による語学研修です。中でもこのファームステイは、子供たちにとっての最大の関心ごとです。3~4人で1グループになって、現地で農業を営むご家庭の一員になります。教員とも完全に離れた状態になりますから、子供たちは自分たちだけで一生懸命、現地の生活に触れていかざるを得ません。
本松氏:子供たちは修学旅行でファームステイや学校交流に備えて、一生懸命勉強します。ただ、実際に行ったら困る場面もあります。でも、グループで協力をしながら、ジェスチャーを駆使したり、絵を描いたり、拙いながらに単語を組み合わせたりすることで、コミュニケーションを図ります。修学旅行から帰ってきた子供たちは、「英語をもっと勉強したい」と口を揃えます。
自分が実際に行ってみて体験して、上手くコミュニケーションがとれた子は「楽しかった、もっと学ぼう」。できなくて歯痒い思いをした子は「悔しかった、勉強しよう」。スイッチの入れどころは子供によって異なりますが、いずれにしても修学旅行は大きな成長の機会になります 。

星野生の成長と創立20周年への展望について
--小学校の6年間で身に付けた力は、卒業以降どのように花開いているでしょうか。
河辺氏:「情操の涵養(情操教育)」、「知の構築(学力養成教育)」、そして今回ご紹介した「国際人の自覚(英語教育)」の3つが星野学園小学校の柱です。この3つは並列で、どれがいちばんということはありません。
よく中学校の教頭から「星野学園小学校の卒業生は挨拶が上手」と言われます。また、「プレゼンテーションが上手」と褒めてもらうこともあります。これらは教養教育を軸にもつ星野学園の学びにプラスして、英語教育をはじめ「伝える」ためのスキルを身に付けることのできる星野学園小学校の教育の賜物だと言えるでしょう。体験学習も多く経験していることもあり、卒業生をリーダーシップの面で高く評価していただくことも多いです。
本松氏:本校では2年生から「過ちて改めざる、これを過ちと謂う」という論語を教えています。そのおかげか、積極性の高い子が本当に多いと思っています。実際、応援団長や児童会長をやりたい人にかなりの数の手が挙がります。中学校、高校に進学してからも、生徒会選挙に出たり、応援団長を務めたりと、小学校で身に付けたチャレンジ精神が根付いているという嬉しい報告をよく耳にします。
--近く創立20周年を迎えられますね。今後の展望についてお聞かせください。
星野氏:これからも小中高の一貫教育の中身をより充実させていきたいと考えています。地に足をつけてこの地で129年教育をやってきた学校ですので、それを土台として、今後もブラッシュアップを重ねていくつもりです。
--ありがとうございました。
星野学園小学校の英語教育は、129年の歴史をもつ学園の教育理念のもと、単なる語学習得を超えた人間教育の一環として位置付けられている。ケンブリッジ大学出版の教材導入とともに実現したオールイングリッシュの授業、ニュージーランド修学旅行での実体験、そして「チャレンジ精神」を重視する指導方針。これらすべてが、12年一貫教育の土台となる6年間で、子供たちがグローバル社会で活躍するための「器」を形成していくのだと、先生たち皆が自信と誇りをもっていることがよく伝わってきた。「英語を使って何をしたいか」を常に意識させる同校の取組みは、来年の創立20周年を機に、さらなる発展が期待される。
「星野学園小学校の英語教育」を詳しくみる「星野学園小学校」公式Webページ