大学全入時代が現実となりつつある中、医学部医学科は依然として「狭き門」だ。現役医学部生たちは、厳しい受験の夏をどう乗り切ったのだろうか。
毎年多数の医学部合格者を輩出している駿台予備学校(以下、駿台)で学び、医学部合格を果たした3名に、限られた時間で自分をどう鍛え、合格への道を切り拓いていったのか、リアルな体験談を聞いた。
【話を聞いた人】
小出泰三朗さん:東北大学医学部医学科3年生(宮城県仙台第二高等学校/駿台予備学校・仙台校)
棚町友香さん:昭和医科大学医学部医学科2年生(学習院女子高等科/同・市谷校舎)
藤井昴史さん:京都府立医科大学医学部医学科3年生(洛南高等学校/同・京都校)
オープンキャンパスで志望校を絞り込む
--皆さんはいつごろ、どのようなきっかけで医学部を目指し、志望校を決めたのでしょうか。
小出さん:僕は小学生のころから人の役に立ちたいという気持ちが強く、感謝されるような仕事に憧れていました。その中でも医師という職業を目指すようになったのは、姉が医学部に進学したことや、母が歯科医師だったことも影響していると思います。
志望校は、目指すなら高い目標をもって頑張ろうと思い、東北大を目標に定めました。
棚町さん:私は高1の夏休みに、学校の先生の紹介で、フレイル(*)の解決策を考える課外活動に参加したのがきっかけです。そこで初めて医学の面白さに触れ、医師という職業はとてもやりがいがあるのではないかと思うようになりました。*フレイル:加齢により心身の活力が低下し、要介護状態へ移行する中間的な状態
昭和医科大学は、富士吉田キャンパスの寮生活がとても楽しそうで、医学部を目指し始めたころから志望校の1つでした。
藤井さん:僕は高1まで、理系を志望してはいたものの、進路に迷っていました。そんな中、ケガで入院し、手術と約半年間のリハビリを経験しました。不安な気持ちでいっぱいだった僕を主治医の先生が励ましてくれて、医師の言葉が患者の心に与える力を実感し、私もそんな医師になりたいと思うようになりました。
京都府立医科大学は、オープンキャンパスに参加した際の雰囲気や、過去問との相性の良さを感じたこと、家から通える国公立大学で経済的負担がもっとも少ないことから、第一志望に決めました。
駿台の授業の良さは、本質から学べること
--どうして皆さんは、駿台を選んだのでしょうか。
小出さん:現役時代は塾に通わず、バスケットボール部との両立をしながら自宅でコツコツと勉強を続けていましたが、合格にはあと一歩及びませんでした。駿台で浪人することに決めたいちばんの理由は、現役時代に受けた駿台模試のレベルの高さです。志望していた東北大学は医学部最難関のひとつであり、それに見合う学習環境が必要だと思いました。また、駿台の授業は1コマ50分間なので、集中しやすいと感じたのも駿台を選んだ理由の1つです。

棚町さん:私は最初、医学部専門予備校への入学を検討したのですが、学費面で断念し、駿台の市谷校舎に見学に行きました。そこでは、スタッフとの距離が近く、気軽に話しやすい雰囲気が自分にあうと感じました。自習室が広く、たくさんあり、学校帰りに立ち寄って勉強できる環境も決め手になりました。
藤井さん:僕は駿台の講師陣に惹かれました。授業で原理から丁寧に学び、しっかりと基礎固めをしてから演習につなげられることが魅力でした。
--駿台の授業の良さや活用法を教えてください。
小出さん:駿台の高卒クラスに通って良かったのは、学力に応じてクラス分けされ、自分のレベルにあわせて指導力の高い授業が受けられたことでした。
特に印象に残っているのが、数学の授業です。現役時代は解法のパターンを当てはめるような勉強法だったのですが、先ほど藤井さんが話したように、駿台では、数学の本質に立ち返り、自分で解法を導き出すという勉強法を教わりました。
棚町さん:学校の授業進度と駿台の授業の難易度に差があり、ついていくのが大変でした。予習と復習に力を入れ、高1では英語と数学を、高2からは化学をプラスし、高3では化学の代わりに物理を加えて、週3回ほど通っていました。
今振り返って良かったと思うのは、苦手だった物理を選抜コースではなく、難関コースで基礎からしっかり固める道を選んだことです。テキストを何度も繰り返し解いたことで着実に力が付き、現役合格につながったのだと思います。

藤井さん:僕は中1の夏から駿台中学部の数学に通い始め、特別得意というわけではなかったのですが、ハイレベルな演習講座にも挑戦していました。
高校では、1年生のときに数学と英語、2年生からは化学も加えて3科目を受講し、3年生まで続けました。学校の勉強を第一に、駿台は学校の予復習や演習量アップに活用し、いずれの科目も本質的な理解を意識して取り組みました。京都府立医科大学の入試は、ただ知識があるだけでは太刀打ちできず、その背景にある原理を理解していないと解けない問題も多かったので、駿台で学んだことがとても役に立ちました。
--先生やスタッフのサポートはいかがでしたか。
小出さん:学習コーチが面談で模試の成績を丁寧に分析し、具体的なアドバイスをしてくれたことで、とても励まされました。登下校時にも声をかけてくださるなど、心強かったですね。現代文の先生には志望理由書などの添削をしていただき、安心して出願できました。
棚町さん:私は受験全体を通して駿台に頼りきっていました。志望校について悩んでいた時期には相談に乗っていただきましたし、模擬面接ではスタッフの方々が何度も事前練習に付き合ってくださったので、本番はあまり緊張せず臨むことができました。また、市谷校舎の高校生クラスには、現役医学部生のクラスリーダーが多数在籍し、昭和医科大学に通う方に実際の受験会場のようすなどを聞くことができ、とても参考になりました。
藤井さん:僕は英語の先生に大変お世話になりました。週1回、英作文講座を受講していたのですが、京都府立医科大学の自由英作文は長文で難易度も高いので、毎週添削をしていただいたおかげで、かなり力が付いたと思います。
毎日コツコツ。模試はペースメーカーに
--医学部受験に向き合ううえで、普段から「これはやっておいてよかった」と思うことを教えてください。
棚町さん:まず、勉強面では、受験直前まで、微積の計算問題、英単語帳、英熟語、英文法に目を通すというルーティンを、1日も欠かさず続けたことです。もう1つは、精神面での工夫です。受験が近づくと焦ることはわかっていたので、周囲と比べず、自分だけに向き合うことを意識するようにしました。
小出さん:僕も棚町さんと同じく、毎日最低限やるべきタスクを作って取り組んだことがよかったと思います。特に、高1から英単語の暗記と、化学と生物の基礎学習を積み重ねていたので、入試では英語と理科が得点源になりました。
藤井さん:僕は基礎の徹底です。医学部受験では難しい問題も多く出ますが、それ以上に「周りの人が解ける問題を確実に解けるかどうか」が合否を分けます。だからこそ、苦手を作らないために、高3の夏までは難問に手を出すよりも、基礎の反復練習に注力していました。小出さんが言ったように、英単語のような暗記系は早めに叩き込み、何度も繰り返すことを意識していました。
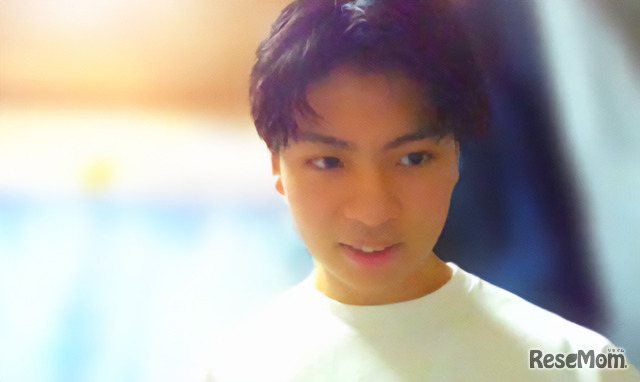
--逆に、「もっと早くやっておけば良かった」と後悔したことはありますか。
小出さん:僕の場合は数学です。理系は数学が苦手だと他の科目の足を引っ張ってしまうので、もっと早くからしっかりと取り組めば良かったと思いました。
棚町さん:私も数学と理科を、もう少し早く取り組んでおけばよかったと感じています。特に物理は高2の終わりまでほとんど手がつけられず、高3になって力学の基礎から勉強を始めたので、もっと計画的に、早い段階からコツコツと勉強しておけたら、受験期にもっと余裕をもって他のことにも時間を使えたのではないかと思っています。
藤井さん:僕が後悔したのは、志望校の共通テストと個別試験の配点割合を把握していなかったことです。個別試験の過去問はきちんと見て取り組んでいたのですが、共通テストも重要だと気づいたのが高3の夏ごろで、ものすごく焦りました。
--どういった模試を受けていましたか。模試の有効な活用法について教えてください。
棚町さん:駿台全国模試(※以下、全国模試)、駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試(※以下、共テ模試)を受けていました。共テ模試は、本番にかなり近い形式で作られているので、形式に慣れることを意識して何度も復習しました。
一方で、全国模試については、判定を気にしすぎないようにしていました。特に全国模試は本当に難しくて、現役生だとなかなか良い判定が出にくいものです。私自身も、ほぼすべてE判定、良くてもD判定くらいで、点数も全然取れていませんでした。でも、模試はあくまで「自分が勉強をどこまで進められているか」を確認するペースメーカーだと考え、模試を通じて自分の苦手分野を把握して、そこを重点的に復習するという使い方をしていました。
小出さん:現役時は学校で案内された模試と駿台の東北大入試実践模試を受けていました。浪人時は、全国模試、共テ模試と東北大入試実戦模試を受けました。
僕は毎回の模試で、小さな目標を作っていました。小さな目標というのは、たとえば「数学のベクトルの問題で8割を目指そう」といったものです。現役時代は判定の悪さばかりに気を取られ、落ち込んで復習する気すら起きないこともあったので、小さな目標を達成していくことで、自信を付けようと考えるようになりました。
藤井さん:僕は駿台の全国模試、共テ模試、京大入試実践模試を受けました。京都府立医科大学には冠模試がなく、実践演習の機会が少ないように感じて不安だったのですが、学校の先生から「京都府立医大志望の子も京大入試実戦模試で腕試しをしている」と聞いて、受けることにしました。同世代のトップレベルの人たちがどういう勉強をしているのかがわかり、今のままではいけないと気づかされました。模試で間違った問題を集めた「直しノート」を作って、苦手な単元や自分のミスの癖などを繰り返しチェックするようにしました。
高3の夏は、苦手を克服し基礎を固めることを第一に
--もうすぐ夏休みですが、受験直前の夏休みはどのように過ごしていましたか。
棚町さん:駿台の夏期講習は、個別試験で使う理科2科目、英語、数学に加えて、初めて国語や論文の講座も受けてみました。予復習が大変で、講習の内容を消化するのにかなり時間がかかってしまいました。
特に数学は苦手なままで、高3の夏になっても難しい問題には手が届かない状況でしたが、駿台のスタッフから「難しい問題が解けないと受からない大学はごく一部。揺るがない基礎があれば十分合格できる」と励ましていただき、夏はとにかく基礎を固めることに集中して取り組みました。
小出さん:僕は浪人生だったので、ある程度基礎が固まった状態で夏を迎えられましたが、それでも「苦手克服」を最優先に、苦手な分野を徹底的に見直しました。たとえば、生物では遺伝の分野で差がつきやすく、生物が得意な自分も苦手意識があったので、講習を取りました。数学も自分の苦手な単元に特化した講座を受講して、重点的に補強しました。
そのうえで余裕があれば、得意科目をさらに伸ばすという方針で、過去問を解いてみたり、難易度が少し高めの薄い参考書に取り組んでみたりしていました。
藤井さん:僕も、苦手をなくすために、不安な分野の演習を繰り返しやっていました。やはり現役生はどうしても時間が足りないので、理科2科目は基礎を中心に反復演習を重ねました。
数学は、特に苦手意識はなかったのですが、が、模試の結果を見返してみると、苦手な分野が散見されたのでしっかりと見直しました。次に出てきたときには絶対に間違えないことを意識し、時間を置いてからもう一度やり直すようにしていました。

--医学部を目指す受験生に向けて、激励のメッセージをお願いします。
棚町さん:入試本番では、受験者の多さに圧倒されて落ち込んだこともありましたが、「何があっても合格する」という強い気持ちをもち続けたことで、合格を勝ち取ることができました。受験勉強は大変ですが、学校では友達と話してリフレッシュし、メリハリを付けながら、決して周りに惑わされず、医師になりたいという思いを忘れず、どんな状況でも諦めずに挑戦し続けてください。
小出さん:数学を最低でも苦手ではないレベルにしておくこと、そして何か1つ得点源になる科目を作ることが大切だと思います。得意科目があると、勉強のモチベーションも上がりますし、本番でも自信をもって戦えると思います。
僕は今、駿台の仙台校でクラスリーダーをしていますが、たくさんの受験生を見てきて感じるのは、最終的に合格するかどうかは、どれだけ自分に自信をもって突き進めるかだと思います。自分を過小評価せず、「やりきった」と胸を張って言えるくらい勉強して、自信をもって本番に挑んでください。
藤井さん:きちんとやっているつもりなのに、成績が全然伸びなくて辛いこともあると思いますが、そういう時こそ、今できていることに目を向けて、小さな成長を自分で評価することを意識してほしいです。もちろん、自分のやり方を見直すことも大切で、実は「やってるつもり」でも勉強の仕方が雑だといつまで経っても力が付かないので、教科書を最初から見直すなど、基礎的な勉強にしっかりと向き合ってください。
医学部受験は本当に大変ですが、焦らず、丁寧に、自分のペースで頑張ってください。
医学部入試というと難易度が高いイメージがあるが、3人が口をそろえて基礎の徹底の大事さを語ってくれたことが印象的だった。ひとり黙々と取り組む姿勢は大切だが、公式の導き出し方から丁寧に指導してくれる駿台の授業は理解を深めるうえで大きな支えとなるだろう。3人の現役医学生の体験談が、受験の天王山とも言われる夏休みを悔いなく過ごす手助けになれば幸いだ。
第一志望は、ゆずれない。駿台式「医学部合格」への道






