2026年4月、関西大学システム理工学部に「グリーンエレクトロニクス工学科(仮称・設置構想中)」が新設される。目指すのは、電子工学の技術を通じて環境問題の解決に取り組める人材の育成だ。
その目標のもと、「半導体」と「環境」を両軸としたカリキュラムを編成。さらに、実験や留学、産学連携を通じて、世界の産業界で即戦力として活躍できる力を養う。関西大学の学是は、学問を実社会に生かす「学の実化(じつげ)」。この学是にふさわしい新たな挑戦について、システム理工学部の梶川嘉延学部長と宝田隼准教授に話を聞いた。
インタビュイー:
梶川 嘉延 教授(システム理工学部・学部長)
宝田 隼 准教授(グリーンエレクトロニクス工学科 就任予定)
電子工学の技術を通じて、環境問題に取り組む
--世界では深刻化する環境問題の解決とテクノロジーの発展との両立が喫緊の課題です。こうした中、グリーンエレクトロニクスとは何か。そして、それは社会にどのようなインパクトを与えるものなのか、わかりやすく教えていただけますか。

梶川先生:まず、「グリーン」は環境、「エレクトロニクス」は電子工学を意味します。つまり、グリーンエレクトロニクスとは、電子工学の技術を通じて環境問題の解決に取り組むことを指します。
欧米ではすでに注目されている分野で、AI分野にフォーカスした「グリーンAI」という言葉も浸透し始めています。
たとえば、近年急速に普及している生成AIは、膨大な処理を行うために大量の電力を消費します。そのため、ある試算では、2026年には日本で生成AIに関連する電力消費量が、日本の総電力と同規模になる可能性があるとも言われています。
こうした大量の電力消費の裏側には、化石燃料の使用やCO2排出といった環境への影響があります。一方で、生成AIは非常に便利な技術であり、今後もさまざまな場面で利用が広がっていくでしょう。
そこで重要となるのが、AIの処理能力を維持しながら消費電力をいかに抑えるかという視点です。この視点をもって半導体の設計や製造の面から環境問題の解決に取り組むのが、グリーンエレクトロニクスです。環境への配慮とデジタル技術の活用の両立を目指すことで、持続可能な社会の実現に大きなインパクトを与えられると考えています。
--グリーンエレクトロニクスを学ぶことで、将来どのような分野で活躍できるのでしょうか。具体的な業種や職種を教えてください。
宝田先生:活躍の場としてまず挙げられるのは、「半導体」の分野です。
実は日本は、半導体を作るための製造装置において世界でトップクラスの技術力をもっており、多くのメーカーが国際的にビジネスを展開しています。さらに、半導体周辺機器の電子部品メーカーや、それらを使う自動車・家電などのメーカーへの就職も想定しています。また、電子機器の制御に使われるソフトウェアを開発する企業でも、グリーンエレクトロニクスの知識や技術は大いに役立つでしょう。
脱炭素社会(カーボンニュートラル)の実現のため、今後はさまざまな業界で、環境と経済の両視点から技術開発ができるプロフェッショナル人材が大量に必要となります。
また、半導体技術の研究や開発には、日本だけではなく、世界中から多くの資金が投入されています。この潤沢な投資は、技術革新と市場の拡大を促しますので、この分野で働くプロフェッショナル人材にとって、活躍の場は多岐に渡ると思います。
環境への配慮という視点をもって半導体について学ぶ
--関西大学では日本で初めての学科となる「グリーンエレクトロニクス工学科(仮称・設置構想中)」が設立される予定です。この新しい学科ではどのようなことを学ぶのでしょうか。
梶川先生:グリーンエレクトロニクス工学科が対象とするおもな学問分野は電子工学です。電子工学の中でも、半導体に関する知識・スキルを習得できるカリキュラム構成で、4年間かけて体系立てて学びを深めます。コンピュータを動かすための基本となる半導体デバイスの設計・製造技術、半導体で構成された集積回路技術、さらには半導体や集積回路を制御・活用するソフトウェアの技術まで、すべてが学びの対象です。
さらに、それらの技術が環境にどのような影響を与えているのかという視点から、「どうすればその電力を減らせるか」「それを最終的に環境問題への改善、たとえば脱炭素社会(カーボンニュートラル)につなげていくにはどうすれば良いのか」について横断的に学んでいきます。
--他大学にはない、グリーンエレクトロニクス工学科ならではの特長を教えてください。
梶川先生:前提として、半導体の製造技術や知識を学ぶ大学や学部・学科は、全国にあります。九州のように半導体製造メーカーが集まる地域には半導体技術を専門に学べる大学もありますし、そもそも多くの大学の理工系学部には電子工学を学ぶ学科があり、半導体についても学ぶことができます。
ただ、電子工学科では、半導体以外にもレーザーや電磁波、通信などの分野も含めて幅広く学びます。それに対して新学科では、半導体技術を中心とした学びが展開されること、さらに、半導体に関する専門性に環境問題への知見を横断させていることが最大の特長です。環境への配慮という視点をもって、半導体やソフトウェアなどの技術を学んでいく。それが、今までになかった新しい学び方なのです。
環境を意識した半導体技術について体系的に学べるカリキュラム
--各学年でのカリキュラムについて詳しく教えてください。
宝田先生:まず、1年次と2年次では、数学・物理・化学といった基礎をしっかりと学びます。そのうえで、2年次から4年次にかけては、電子工学の専門的な知識と技術を体系的に学んでいきます。
新学科が従来の電子工学科と異なるのは、学んだことを「使いこなせるか」を強く意識している点です。特に、ソフトウェア分野にはかなり力を入れて進めていく予定で、1年次から3年次までは毎学期、プログラミング実習を設定しています。
カリキュラムは、次の4つの柱に沿って組んでいます。
デバイス物性:半導体の根本的な性質や仕組みを原子や電子のレベルから理解する分野
装置・加工・計測・制御:半導体デバイスをどのようにして製造するかに関する分野
アナログ・デジタルの集積回路:製造したデバイスをハードウェアとしてどのように活用するかを考える分野
数値計算・情報:集積回路を、ソフトウェアとどう連携するかを学ぶ分野
この4つの柱に加え、環境問題を意識した授業を各学年に設けています。
--環境問題を意識した授業とはどのような内容ですか?

宝田先生:具体的には、1年次から3年次まで「グリーンエレクトロニクス概論」や「グリーンエレクトロニクス応用」といった科目を設けています。これらの授業では、その年次で学ぶ半導体技術が、どのように環境問題に関わっているのか、さらにはその解決に向けて、今どのような技術が求められているかを学びます。授業は、学科の教員だけでなく、半導体関連の企業や環境問題の専門家など、外部からも有識者を招いてリレー形式で講義を行う予定です。
--関西大学では学問を実社会に活かす「学の実化」が学是ですが、新学科でも実社会との連携は積極的に行われるのでしょうか。
梶川先生:もちろんです。学問として学ぶだけでなく、4年次では、実際に半導体関連企業で働くリアルな感覚をつかむ機会として、産学連携にも取り組みます。
具体的には、半導体製造装置を扱う企業などにご協力をお願いし、実際の現場が抱える課題を学生に共有してもらいます。それに対して学生は、3年間で学んだ知識や技術を使って解決を目指すPBL(Project Based Learning=課題解決型学習)形式で実践力を磨いてもらいます。
--世界的に半導体の技術をもつ人材が不足していると言われています。将来を見据えて、新学科ではグローバルな視点がもてるような取組みも用意されていますか。
梶川先生:システム理工学部の電気電子情報工学科で実績のある「グローバル人材育成プログラム」を新学科で実施していく予定です。
2年次では、半導体技術で世界をリードする台湾へ約3週間の短期留学を計画しています。本学は台湾にも協定校があり、特に理工系の分野では著名な大学と協定を結んでいます。現地では、世界各国の学生と4か国混成のチームを作り、大学の先生から出される課題に取組みます。
宝田先生:日本人学生は本学の学生のみで、各チームに1人ずつとなるため、自ら積極的に英語でコミュニケーションを図る必要が出てきます。ですが、最初から英語が得意である必要はありません。この経験が、英語学習への動機づけになれば良いと思っています。
また、このプログラムで学ぶのは、語学だけではなく、エレクトロニクス技術をテーマにした国際協働です。半導体業界は多国籍化が進んでいて、実際に働く現場では国籍も文化も違う人たちと協働するのがむしろスタンダードです。大学生のうちからそうした環境を体験してもらうことで、グローバルリーダーとなれる人材を育てたいと思っています。
なお、3年次では、ポーランドの工科大学に約1か月間の短期留学制度を用意し、よりハイレベルな内容に取り組むことが可能です。
--新学科の設立に合わせて、「クリーンルーム」も設置されるそうですね。
梶川先生:はい。新学科で半導体技術を中心に学ぶうえで、半導体を実際に作るための工程、いわゆる「製造プロセス」を、実体験を通して学ぶ必要があると考えました。
半導体の製造に必須となる「クリーンルーム」を保有している大学は他にもありますが、ほとんどが研究目的であり、学部生が利用するのは難しいところが多いと思います。そういう意味でも、教育専用で、グリーンエレクトロニクス工学科の全員が、学部生の段階から「クリーンルーム」で実験できる点は、新学科の大きな特長といえるでしょう。
梶川先生: 特に半導体関連企業では、実際に製造工程に触れた経験をもつ学生は非常に高く評価されます。現場で求められる実践的な力を育むためにも2、3年次での「クリーンルーム」を使った実験・実習も含めて、体験型のカリキュラムを大学でしっかりと用意することはとても重要だと考えています。

グリーンエレクトロニクス工学科はこんな人におすすめ!
---新学科は、進路がまだはっきりしていない中学・高校生にとっても、自分が社会課題の解決に役立てるという点で、大学選びの新しい基準になりそうですね。新学科にはどのような人に挑戦してもらいたいですか。
梶川先生:これまで電子工学と環境問題はあまり結びつかないように思われてきましたが、今日お話をしてきたように、実は非常に深い関わりがあります。「環境問題のために何かしたい」という気持ちをもっている人には、ぜひこの学科に来てもらいたいです。
また、今は音楽、スマホ、ゲームなど、自分の日常生活に半導体や電子工学の技術がたくさん詰まっています。「スマホの電池をもっと長持ちさせるには?」「生成AIってどうやって動くんだろう?」といった疑問を出発点に、その仕組みを理解したいと思う人にもぴったりだと思います。
--大学入試に向けては、どのような勉強が必要ですか。 そしてそれは、大学入学後にどのように生かされるのでしょうか。
梶川先生:電子工学を基盤とするので、数学と物理はしっかり学んでおいてほしいです。数学であれば数Ⅰから数Ⅲ・Cまで、物理も物理基礎だけでなく、より深い内容を扱う物理まで学習しておくことが望ましいです。また、現在高校では「情報」という科目が導入されています。この教科を通じてコンピュータやスマホといったデバイスの仕組みに関心をもって学んでおくと、大学でも役立つでしょう。
宝田先生:どの程度の学力が求められるのか、不安に感じる人もいるかもしれませんが、関西大学の理工系3学部では、入学時に数学・物理・化学の基礎学力調査を行っています。その結果に応じて、基礎と標準の2クラスに分かれ、基礎の学生には、追加の補習講座を用意してフォローする体制を設けています。ですから、もし理系科目に苦手意識があっても、入学後にしっかりと学力を伸ばせるように大学がサポートしますので、どうか焦らず、まずは大学入試に向かって頑張ってもらえたらと思います。
また、高校で学ぶ数学、物理、情報といった科目では、単に公式を暗記するのではなく、なぜこのような公式になるかを考えてみる、根本原理を理解するように努めてみてください。このような思考をもつことで、論理的思考力が培われ、大学入学後の学びにも大いに生かされるでしょう。
世界中から求められる半導体×環境のプロフェッショナルを育てたい
--新学科では、どのような人材を育てていきたいですか。
宝田先生:脱炭素社会(カーボンニュートラル)への変革を主導し、環境に配慮した持続可能な成長を推進できる知識やスキルをもつGX(グリーントランスフォーメーション)人材を育成していきたいですね。
梶川先生:技術の発展を追求するだけでなく、環境への配慮を忘れず、より高い視座から複眼的に考えられる技術者・リーダーを育てたいですね。そして、新学科で学んだ卒業生には、日本だけでなく世界の半導体産業に貢献できる人材になってほしいと願っています。
--最後に、これから進路を決める中高生やその保護者にメッセージをお願いします。
梶川先生:今後、GX人材は世界中から求められるようになります。ぜひこの新しい学科の先駆者として、未来への扉を開けに来てください。そして、お子さまが少しでもこの分野に興味を示していたら、ぜひ応援してあげてほしいと思います。
--ありがとうございました。
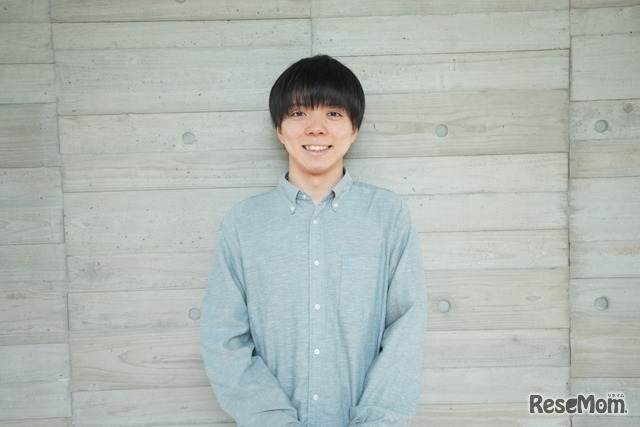
関西大学システム理工学部 電気電子情報工学科出身(関西大学理工学研究科 システム理工学専攻 電気電子情報工学分野 博士課程前期課程在籍)米田 暁さん
電気電子情報工学科では、授業で学んだ内容を実験で実際に試せるカリキュラムになっており、理論と実践がしっかり結びつき、理解が深まりやすかったです。新しく設置されるグリーンエレクトロニクス工学科は、幅広い電子工学の分野から「半導体」を「環境問題」と絡めて学べる点が秀逸です。目指す方向や社会的な役割が明確なので、自分の興味や関心と重なれば、進路としてとても選びやすい学科だと思います。
新学科では、半導体技術と環境の分野横断型の学びが提供されるだけでなく、クリーンルームでの実験や産学連携、「グローバル人材育成プログラム」を通して、即戦力となる技術力も培える。今後ますますの発展が期待される半導体業界で、国境を越えて活躍できる人材を育てようとする意志が随所に感じられるカリキュラム編成だ。新学科の取組みに今後も注目していきたい。
システム理工学部 グリーンエレクトロニクス工学科|関西大学





