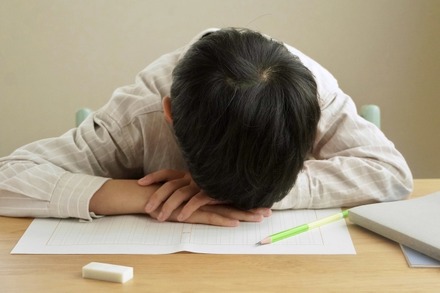夏休みの宿題で討伐困難な目標のひとつは「読書感想文」だろう。本を読むだけでも大変なのに、原稿用紙数枚分の作文課題を課される。これは、普段から文章を書きなれていなければ、大きな障壁となるだろう。
読書感想文の難易度はリーディングとライティングの2つに集約される。逆に言えば、これらを攻略できれば、読書感想文を数日以内に終わらせることも可能となる。つまり、超えるべき関門は3つだ。
1.本を読む、やる気を出す
2.本の内容を理解する
3.理解した内容を書き記す
今回は読書感想文が簡単に書ける「読書感想文のやっつけ方」を、ステップごとに解説していく。どうか諦めずに立ち向かう際の参考にしてほしい。
STEP1:本を選ぶ
まずは本を選ぶ。ここで重要なのは、「本を読め」と言われても、動画メディアに慣れ切った子供たちは、もはや活字に興味を示さない可能性があることだ。難しく退屈なものではなく、面白く魅力に満ちたものだと説明する必要がある。親が本を読む家庭ならば、かつて自分が読んだ本を勧めるのはひとつの手だろう。ここではせめて読むハードルが低くて済むような本を選ぶうえでのポイントをお伝えする。
1.短めで挿絵が多い本を選ぶ
文字数が減れば減るほど読む際のハードルが下がることは間違いない。一口に小説といっても、本によって挿絵の枚数や文字の大きさは異なる。『かいけつゾロリ』や『はれときどきぶた』のような挿絵メインの本であれば、見開きの文字も少ないはず。単純に文字を読む負担が減るし、どんどんページをめくっていけるので、「読書している感」を演出することができ、モチベーションも上げやすい。
2.あらすじがネットに落ちている本を選ぶ
読書にハードルを感じる子にとって、「中身がわからない本を読む」こと自体がストレスとなる可能性がある。実際、「知らないことを知る」ためには、十分な知的好奇心と体力が必要になるので、この感覚は間違いではない。そのため、本を選ぶ際には、あらかじめあらすじをネットで検索してしまうと良い。悪く言えば「ネタバレ」だが、私はこれを補助輪のようなものだと感じている。内容をあらかた把握したうえで、あらためて本を読んでみる。たったそれだけで、内容の把握にかかる時間を大きく減らすことができるからだ。その特性上、新刊ではなく、昔からある伝統的な本のほうが、より調べやすいためお勧めできる。
3.マンガやアニメ、ゲーム作品のノベライズを選ぶ
興味のある内容から派生して本に行きつくのもよいだろう。たとえば、先日劇場版最終章が公開された『鬼滅の刃』などもさまざまなノベライズが出ている。ノベライズの優れたところは、「舞台設定はどこで、時代背景はいつごろで、文明・文化レベルはこれくらいで、こんな人が主人公で、仲間はこれで~」と、いちいち説明されなくても済む点だ。まったく新しい世界ではなく、「知っている世界・知っているキャラたちの、描かれなかった隠れた活躍」をうかがい知ることができるので、読むハードルが低いのに、読み進めるモチベーションを高く保ちやすい。ぜひ好きな作品のノベライズを探してみてはいかがだろうか。
4.短編集を選ぶ
それでも本を1冊読むのが厳しいのであれば、短編集を推奨する。星新一のショートショートがお勧め。短編集であれば、「特にこの話が面白かった」と特定の話だけについて記述しても不自然ではない。もちろん、すべての話に目を通してほしいが、場合によってはいくつかの話を読み飛ばしても、読書感想文を完成させられる。星新一のショートショートは短編とはいえ短くても見開き3~5ページはあるが、本を一冊読むよりも負担は少ないはず。
子供たちが読書を、そして作文を苦手に捉えてしまう最大の理由は、読み・書きそれぞれの経験が乏しいことにあると推察できる。やったことがないからこそ、高尚で難しいものだと思い込んでしまう。だからこそ、これらに取り掛かるハードルを下げるには、「思っているよりも簡単である」と理解させることだ。具体的には、内容が簡単だったり、既に知っていることの延長だったり、内容量が少なかったりする本を選ぶとか、親が実際に読書・作文に取り組んでいる姿を見せるとか、そういった対処方法が考えられるだろう。
これらのポイントを元にしながら、1日目は本を選ぶ。できれば、実際に本屋に足を運んで、中身を確認しながら選んでほしい。本屋に赴く最大の利点は「知らなかったけれど、面白そうな本と出会える」ところ。何よりも、自分が読みたいと思った本を読むことが大切だからこそ、一期一会を大事にしてほしい。
また、できれば1日目の段階から読書を始められるようにすると良い。読書感想文は本を読んでからが本番なので、読むタイミングも早いに越したことはない。今回の計画では3日のうち、1日を「本を読む日」としているが、この1日で終わらせる自信がないのであれば、中日を2日や3日にするなど、調整してほしい。また、ポイントでもお勧めしたように短編集の本を買ってくれば、読書にかかる時間を減らせるだろう。
STEP2:本を読む
次は本を読み進める段階に入る。ここを鬼門に感じる方も多いだろうが、逆をいえば、ここさえ終わらせれば、読書感想文の半分は攻略したも同然。本を読む際には以下のポイントに気をつけてほしい。
1.あらすじを把握する
STEP1でも書いたが、あらかじめあらすじを頭に入れながら読み進めるようにする。いわゆる「ネタバレ」に当たるが、今回の目的は「素晴らしい読書体験をすること」ではなく「作業として読書感想文を終わらせること」なので、効率よく読書を行う必要がある。そのためには、読み進める本に関する情報をネットで集めて、どんなストーリーで、どのように展開して、どう終わるかを頭に入れたうえで読み進めたほうが、すんなりと情報を把握できるだろう。この際、舞台設定と登場人物の把握を中心に進めると、捗るだろう。つまり、「いつ・どこの話なのか」「主人公や敵役は誰か」「どんな事件が起きるのか」などである。
2.本を読んで印象的だった場面に付せんを貼る
文章はゼロから考えるものではない。慣れないうちは、ある程度決まった型の中に、当てはまりそうな内容を書き入れて作るのが基本。読書感想文の場合も、ある程度決まり切った型を基にして、その中に本の中の印象的な場面を1つか2つ程度入れてあげると、それらしくなる。そのためには、あらかじめ「どの部分を入れるか」決めておく必要がある。そのため、本を読んでいる段階で、「面白い」と感じたページに付せんを挟んでおくと、後から見返しやすくなるだろう。
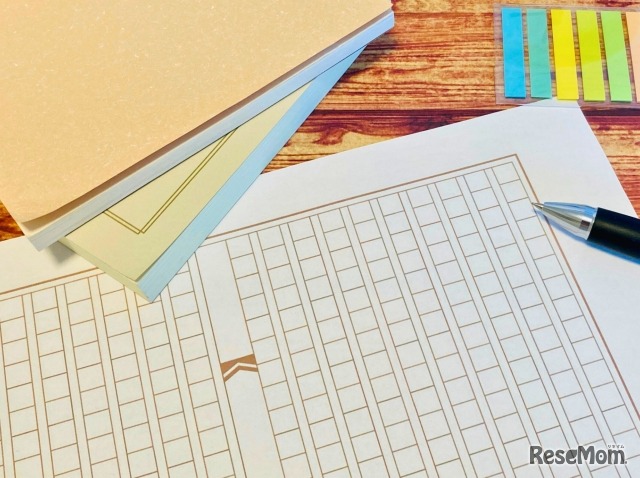
3.読み込まない
文章を読む際のコツは、読み込まないようにすること。意味がわからない文章があっても良いし、そういう文章は読まなくて良い。それくらいの意識で、どんどん読み飛ばしていった方が、モチベーションを維持できる。読書が苦手な人や嫌いな人ほど「完璧な読書」を求めるが、読書が得意な人などは、そこまで細部にこだわらない。一行や二行程度なら読み飛ばしても、全体の流れを把握するうえで不便はない。理想はすべての行のすべての単語までしっかりと読むことだが、そんな理想にとらわれず、「3回読んでも意味がわからない」と感じたら、どんどん読み飛ばそう。
これらのテクニックを使って、1日以内に読み終えてほしい。逆を言えば、ここで読み終えられる程度には短めの本にした方が良いだろう。長い本を読めることは、立派かもしれないが、読み終わらないリスクがある。短く簡単な本だとしても、早く読書感想文を仕上げたほうが立派だ。
STEP3:読書感想文を書く
本を読み終えたら、いよいよ読書感想文を書き始める。とはいえ、ゼロから文章を考えるのは難しい。
ずばり作文のコツを言うなら、「パクる」ことだ。自分の作文能力に期待してゼロから生み出すのではなく、すでにある素晴らしい文章をマネして、それらの一部を改変しながらオリジナルの文章にしていく。実際に、筆者の知り合いの新聞記者の方も、新人時代は先輩記者の書いた記事を写して「新聞流の作文術」を学んだという。うまい文章はうまい先人のパクリから生まれる。ゼロから生み出せるのは天才だけだ。
では、読書感想文は何を参考に真似れば良いのか。ここでは、誰でも読書感想文が書けるように、文章のフォーマットを用意した。ここの空欄部分に、当てはまるイベントや名称を差し込んでいけば、誰でもそれらしい読書感想文が書けるようになるだろう。困ったときの最終手段として活用してほしい。
【読書感想分のフォーマット例】
タイトル:「(本の名前)」を読んで
私は、「(本の名前)」を読みました。この本を選んだのは、(理由)だからです。
この本は(あらすじ)な話が描かれますが、私はその中でも、特に「(付せんを貼ったシーン)」の場面に(感動し・驚き など)ました。なぜなら、(理由)だからです。私は(自分の体験)ということがありましたが、この本の主人公のような振る舞いができれば、(より良くなった・もっと頑張れた など)と思いました。
私がこの本の中でいちばん好きなキャラクターは(好きなキャラクター)です。なぜかというと、彼・彼女は(理由)だからです。私自身は(そのキャラと似ている部分がある・ない)ので、特に魅力に感じられました。
私はこの本を読んでから、(感想)と考えるようになりました。これまで私はこのようなことを考えたことがなかったので、「(本の名前)」を読むことで、新しい考え方を学ぶことができたのだと思います。
とても面白い本だったので、友達にも今度勧めてみたいです。
フォーマットだけで400文字程度あるので、十分な文字数が稼げるだろう。あとは個々の空欄になっている部分に、あてはまる内容を書き込んでいけば、誰でも簡単に読書感想文を書きあげることができる。
繰り返すようだが、今回の目的はあくまで「なるべく素早く読書感想文を書きあげること」であるし、文章の練習のためには「文章の型を知る」ことが早道なので、今回はフォーマットを呈示している。これを基にして、自分でさまざまな作文に対する対応力を身に付けていってほしい。
強敵と思える読書感想文も、工夫をすれば、3日以内に終わらせられる。本を読み、文章を書くことに不自由しなければ、むしろどの宿題よりも簡単に、一瞬で終わらせられるだろう。宿題に時間を取られすぎることなく、自分のやりたいことに集中することが、夏休みを充実させる第一歩だ。この記事を通して、読書感想文を攻略してほしい。