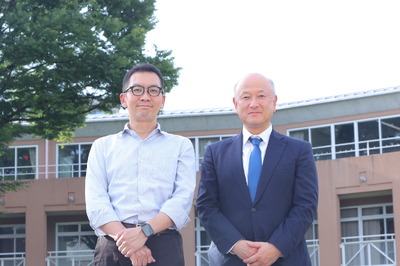2025年に「三田国際科学学園」へと校名を改めた同校は、2015年の開校以来これまで「三田国際学園」としてグローバル教育とともにサイエンス教育にも力を注いできた。中でも「メディカルサイエンステクノロジークラス・コース(MSTC)」では、生徒たちがサイエンス分野の研究活動を通じて、実践的な力を育んでいる。
今回は、三田国際科学学園 教頭・MST部長の辻敏之先生、そしてMSTCに在籍する高校2年生のM.Sさん、A.Nさんに、クラス・コースの概要や研究の進め方、現在の取組みについて話を聞いた。
【インタビュイー】
辻敏之先生:三田国際科学学園 教頭、MST部長
M.Sさん:三田国際科学学園7期生。現在、高校2年生。ドローンのプロペラの静音性について研究している。東京大学「UTokyoGSC-Next」に参加中。
A.Nさん:三田国際科学学園7期生。現在、高校2年生。放線菌について研究している。「つくばScience Edge2025」にて創意指向賞を受賞。
「好き」「楽しい」の気持ちが、MSTC受験のきっかけに
--それぞれの関心で専門的なサイエンスを追究しているお二人は、なぜ三田国際科学学園を志望されたのでしょうか。
M.Sさん:中学受験のため、小4から塾に通ううちに理科の面白さに気づき、自然と点数も伸びていきました。「理系に力を入れている学校で、良いところがあれば行ってみたい」と思っていたところで出会ったのが、三田国際学園(当時)でした。MSTCは理科と算数だけで受験でき、自分の得意科目を活かせると感じたことも大きな魅力でした。さらに、小5、小6のときに二度学園祭を訪れ、サイエンス部の体験がとても楽しかったことや、ラボが充実していて環境が整っていることも、志望の決め手となりました。
A.Nさん:私も同じく小4から中学受験の塾に通っていました。自分では気付かなかったのですが、当時の私は算数の問題をすごく楽しそうに解いていたようなんです。それを見た先生から、「三田国際学園(当時)のMSTCを受けてみたら?」と勧められました。確かに、算数は好きだったので、「自分が輝ける場所のある学校かもしれない」と感じて受験を決めました。
--幼少期~小学生時代に熱中していたものや、当時の学習スタイルについて教えてください。
M.Sさん:幼少期から、工作やプラモデルなど、手を動かしてモノを作ることが好きでした。小学校では理科の授業が好きで、中学受験の勉強が始まると、物理や化学の問題を解くことが楽しくなりました。でも、自分でコツコツ取り組むのは本当に苦手で、受験勉強も自分から進んで取り組んだ記憶はありません(笑)。
A.Nさん:私はバレエや水泳など、体を動かすことが好きで、いろんな習い事で忙しい毎日でした。中学受験のための塾では宿題をこなすのが精一杯でしたが、小6の夏からは自習室で勉強するようになって、塾の先生にもサポートしてもらいながら前向きに取り組めるようになりました。
生徒の興味を起点に、各分野のスペシャリストが伴走
--現在のご自身の研究テーマと、そのテーマに興味をもったきっかけを教えてください。
M.Sさん:MSTCでは、高1でクラス全員が一斉に研究テーマを決めることになっています。そこで私はまず、「自分は何に興味があるんだろう?どんなテーマなら楽しんで研究できそうかな?」というところから考え始めました。 そのときに、ふと頭に浮かんだのが「ドローン」でした。小学生のころから空を飛ぶものに興味があり、いつだったか公園でドローンを飛ばしている子たちを見かけて、「面白そうだな」と感じたのを思い出したんです。
また、学校で有志団体の「映像班」に所属していたことも、ドローンをテーマにするきっかけの1つでした。本校の映像班では、入学式や体育祭などの学校行事を撮影して配信する活動をしています。カメラなどの機材がかなり充実しており、さらに「ドローンも使えたら良いな」と常々思いつつも、飛ばすときのプロペラの騒音が撮影の際のボトルネックになっていました。 空飛ぶものへの興味と身近な課題の解決がうまく掛け合わさり、「ドローンの騒音を抑える研究をしよう」とテーマが決まりました。
A.Nさん:私は、理科の実験中にふと浮かんだ疑問からテーマを決めました。私が気になったのは、生物を培養する際にシャーレ上で使う寒天を主成分としたゼリー状の培地についてです。文献を調べてみると、実験で使う培地のほとんどは寒天濃度が1.5~2.0%で作られており、「なぜこの濃度なのだろう?」という疑問が湧きました。そこで先生に話してみたところ、「そんなことは考えたことがなかった」と言われ、寒天の濃度と菌の生育に関する研究をテーマにすることにしました。
辻先生:研究テーマを決める際には、先輩たちが取り組んできた研究テーマを紹介することもありますが、指導者の専門分野や過去の事例に縛られず、生徒自身の興味から自由に設定してもらっています。一方で、制限がない分、テーマを決めるのは非常に難しく、指導者側にも本気のサポートが求められるという側面もあります。しかし、そのプロセスそのものも、生徒たちにとってはかけがえのない成長の機会になっていると言えるでしょう。
現在、学内の常勤教員と学外の専門家、あわせて8名でおもに研究の指導を行っています。博士号をもっていたり、大学などの研究機関に所属していたりと、研究者として実績のあるメンバーです。工学、生物学のほか、動物心理学、物理学、情報学、数学、脳科学など、幅広い分野の指導者がそろっています。
東大「UTokyoGSC-Next」に参加、JAXA研究者から助言も
--M.Sさんは、ドローンの静音化についての研究をどのように進めていますか。

M.Sさん:学校には必要な機材がひととおり揃っていて、プロペラの製作や実験器具の作成、データの収集など、ほとんどの作業は校内で完結できます。「ものづくり」のスペシャリストである先生に技術面のアドバイスを受けながら、実験器具の開発など実験で使う装置もすべて自作しています。
--M.Sさんは、東京大学の「UTokyoGSC-Next」*に参加しているそうですね。どのような経緯で参加することになったのでしょうか。学校での研究との連続性や棲み分けについても教えてください。
M.Sさん:東京大学で研究ができるのは楽しそうだなと思ったこと、過去にも先輩がこのプログラムに参加していて、先輩や先生から「応募してみたら?」と勧めてもらったことが応募のきっかけです。書類を書き始めたのは高1の4月ごろで、一次選考が6月初旬にありました。その後も学校で研究を進めながら内容をブラッシュアップし、夏休み明けに中間審査、11月には面接を含む最終審査がありました。 現在は工学部 航空宇宙工学科の研究室に所属し、東大の先生から直接指導を受けています。Zoomで東大の先生方に進捗状況を報告し、アドバイスをいただきながら、研究自体は学校で進めています。僕が研究しているプロペラは、ある先行研究で開発されたものを参考にしているのですが、東大の先生の紹介で、その開発者であるJAXAの研究者の方とも接点をもつことができ、ご指導いただける機会がありました。とても恵まれた環境だと感じています。
*東京大学が実施する、未来社会をデザインできる革新的な科学技術人材を育成するための小学校高学年~高校生を対象とした研究活動プログラム。小中学生対象の第1段階ではアクティブラーニング型学習と研究活動を行い、おもに高校生対象の第2段階ではSTEAM型ワークショップなどを通して研究計画を練り、第3段階では東京大学の研究室にて自ら研究活動を行う。
部活と両立しながら研究、「つくばScience Edge2025」で受賞
--A.Nさんは、どのように研究を進めていますか。

A.Nさん:私は陸上部の部長で、部活動を最優先にしたいと考えています。そのため、どうしても研究に使える放課後の時間は週2回程度と限られてしまいます。ただ、やるからには時間がないことを言い訳にせず、しっかり成果を出したい。その思いから、高1の夏休みは部活が終わった後も学校に残って研究を進めるようにしました。また「仲間を増やして研究を発展させたい」と思い、一緒に研究してくれるメンバーも探しました。現在は私と後輩2人の3人のチームで研究を進めています。
--A.Nさんは「つくばScience Edge2025」**で創意指向賞を受賞されたそうですね。参加のきっかけと、参加したことで得た学びを教えてください。
A.Nさん:「つくば Science Edge 2025」には、学校の年間プログラムの一環として、MSTCの高1は全員がエントリーすることになっています。それぞれポスターセッションで発表したり、展示したり、研究を発信するのですが、私はエントリー後の選考で大きなホールでプレゼンテーションをする8組のうちの1人に選ばれました。学校の先生にチェックしてもらいながら何度も練習したので、発表そのものは緊張感なく臨めましたが、質疑応答については「何を聞かれるのだろう」と不安がありました。
結果的に、審査員の皆さんからは「世界的にも新しい観点で、発想が素晴らしい」というお褒めの言葉をいただき、創意指向賞までいただくことができました。大きな会場、大勢の前での発表はとても良い経験になりましたし、さまざまな分野の研究に取り組む他校の人たちとも出会えて視野が広がり、刺激をもらいました。
**JTBと茨城県科学技術振興財団が共催し、文部科学省や科学技術振興機構(JST)などが後援する、中高生が授業の課題研究やクラブ活動で取り組んだ研究をもとに、科学に関するアイデアを発表するイベント
主体的かつ自由に「好き」を深め、成長できる環境
--MSTCの特徴を教えてください。

辻先生:MSTCでは、学校側が「こういうことを学んでほしい」と明確なゴールを設定するのではなく、生徒ひとりひとりが自分の興味を起点に学びを深めていくことを大切にしています。
大学の研究室では皆専攻が同じなので、どうしても似通ったテーマが並びがちですが、MSTCは、1つの空間に多種多様な興味が共存している点が大きな特徴です。微生物を研究している隣でプロペラを回していたり、別の机ではプラナリアを切っていたり、物理の難問に取り組んでいる生徒がいたりする。そうした空間の中で、隣で取り組んでいる研究の話が何となく耳に入り、「こうすればできるんじゃない?」とふと口にした一言が、思わぬ化学反応を生み、研究が進展することもあります。
このように、偶然の重なりから解決の糸口が見つかるような心踊る体験こそが、MSTCで学ぶことの面白さであり、他にはない魅力だと感じています。 もちろん、研究に取り組む中で、実験の準備から後片付けを含めた時間管理の難しさや、部活動との両立で苦労するなど、決して楽しいことばかりではありません。けれども、そうやって試行錯誤を重ねていくことも、生徒たちの長い人生に役立つ大切なライフスキルを育んでいるのだと思います。
--辻先生をはじめ、修士号・博士号をもつ先生方が複数いらっしゃるというのも、三田国際科学学園の大きな魅力です。専門分野での研究経験のあるお立場から、生徒さんたちへの接し方として意識されている点があれば教えてください。
辻先生:「答えを教えない」ということは、常に意識しています。研究計画書や大会へのエントリー書類の添削などをする際には、生徒本人の言葉や考えを尊重し、私たちの価値観を押し付けないようにしています。「ちょっと違うんだよな…」と思っても、その段階ではあえて指摘せず、生徒自身が気付けるまで待つことも少なくありません。 また、生徒を高校生としてではなく、研究者としてリスペクトしながら関わることも心がけています。ですから、研究に関して「時間がないからできない」と言われたときは、「なぜ時間がないのか」と、あえて厳しく問うこともあります。けれど、我々教員は常に生徒と真剣に向き合っているので、そこには揺るぎない信頼関係があります。ですから生徒たちは厳しい言葉を言われることがあってもそれを素直に受け止め、その言葉をバネにしてさらに成長していくのです。
--最後に、三田国際科学学園に関心を寄せている受験生と保護者の方にメッセージをお願いいたします。
A.Nさん:三田国際科学学園には、自分が好きなこと・興味のあることに思い切り取り組める自由な環境があります。スポーツでも音楽でも、自分の興味や関心を起点に、探究をとことん楽しんでいる人たちが身近にたくさんいて、いつも刺激を与えてくれます。誰かが決まった正解をくれるわけではないので、何をするにしても主体性が求められますが、自分が「やりたい」と思ったことに対して全力で応援し、サポートしてくれる学校です。
M.Sさん:この学校の授業は、他の学校と違うと感じるかもしれません。それは、生徒が自分で考える場面がとても多いからです。ひとりひとりが常に、「どうすれば良いだろう」と自分なりに考えて工夫し、実践し、検証するという姿勢が、学校全体に浸透しているように思います。この姿勢はMSTCでの研究活動にも活かされていますし、きっと社会に出ても役立つ大切な力を育んでもらっているのだと思っています。
辻先生:2人の話にもあったように、この学校は自分自身が何を面白いと感じるか、どんなときに楽しいと思えるかといったことを、常に問われ続ける場だと思います。中1のときから自分と向き合い、自分の興味や関心とていねいに向き合ってきたからこそ、今日ご紹介したような研究にもつながっているのです。
今「我が子の得意なことって何だろう」「うちの子に好奇心ってあるのかしら」と心配されている方に伝えたいのは、むしろ普通だった子こそ、あるきっかけでスイッチが入り、大きく成長することが、この学校では決して珍しいことではないということです。お子さまに、自分が楽しいと感じる、心がワクワクする瞬間を大切にしてほしい、あるいはそういう生き方をしてほしいとお考えのご家庭は、ぜひ一度、本校に足を運んでほしいですね。学園祭では生徒たちの活動を実際にご覧いただけますし、三田国際科学学園としての教育の軸を感じていただける機会にもなるでしょう。そうした環境をご自身の目で見て、感じていただけたら嬉しいです。

--ありがとうございました。
研究を進めることは決して楽ではないはずだ。けれど今回の取材を通じて、先生と生徒が同じ「研究者」としてフラットに関わり合い、まるで遊び仲間のように一緒に研究を楽しんでいるようすが伺い知れた。そんな先生と生徒との距離の近さと、校内に漂う明るく前向きな空気感が、とても魅力的だと感じた。グローバル教育とサイエンス教育の両輪で、未来を切り拓いていくユニークな人材の輩出を期待したい。
「三田国際科学学園」について詳しくみる