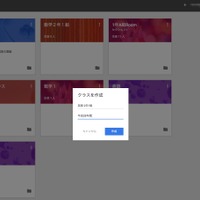先生にもっと便利を…世界で拡がる「Google Classroom」の機能と利便性
教育のICT化に伴い、さまざまなデジタルサービスやツールが教育現場でも取り入れられるようになっている。Google for Education 日本統括責任者の菊池裕史氏に、デジタルサービスを教育現場で使う意義や活用例を聞いた。
教育ICT
先生
advertisement

--Google Apps for Educationと統合した機能はほかに何がありますか。
メインはドライブとの連携機能です。たとえば先生が課題を出したとき、提出するタイトルも生徒によってまちまちだったり、誰が未提出なのかわかりづらかったりします。Classroomを使うと、Googleドライブ内にClassroomフォルダーが自動で作成され、クラスごとのデータがすべて保存されるようになります。これはClassroomの大きなメリットです。複数のクラスを担当していても、自動でクラスごとに課題がまとめられるというわけです。
なお、課題は生徒のGoogleカレンダーに反映されます。これにより、課題の伝え忘れといった人為的ミスも減らせます。自分のクラスごとのカレンダーが作成されるので、クラスごとの課題を参照できるようになっています。
また、ストリームで課題を生徒に出す際にも便利な機能があります。たとえば、指定の形式で課題を出してもらいたい場合、あらかじめGoogleドキュメントなどで作成したテンプレートを指定するだけで、そのテンプレートをクラスの生徒全員に自動で配布できます。
--それはとても便利ですね。わざわざひとりひとりに送らなくてよいのですね。
そうです。さらに、ひとつのファイルをクラス全員で共有することも可能です。先生が作った課題に対して、みんながアクセスして編集を行うといった使い方もあります。「Education版をもっと使いやすくしてほしい」という先生の声を受け、アプリをもっと学校の中で集中管理できるようにしたものが「Google Classroom」というわけです。
生徒は課題を書き終えたら「提出」のボタンを押すだけで、ファイル名に自動で自分のユーザー名が入った課題ファイルが、先生側のクラスのフォルダーに届くようになっています。先生は、フォルダー側で誰が未提出なのかもひと目でわかります。
先生は課題に対して評価をつけることも可能です。点数は先生側で「10点満点」や「5点満点」といった設定ができ、それぞれの課題に対して評価がつけられます。また、コメントもつけられるようになっています。
【次ページ】「常に最新機能を使える」というメリット…多忙な先生と生徒に配慮
advertisement
【注目の記事】
関連リンク
この記事の写真
/
advertisement